こんにちは。
最近、世界中のリベラル派と見られる国家元首クラスの人々の言動に違和感を持たれることはないでしょうか? リベラル派というと寛容で個人の自由を尊重する人たちのはずなのに、やっていることはまったく違うんじゃないかと思うことが多々あるような気がします。
たしかに我々日本人がリベラル派という言葉に抱くイメージとはずいぶん違うのですが、じつはリベラル派の本性は、我々が描くイメージではなく、いま世界中でリベラル派の政治家たちがやっているかなり強引な自分たちの主張の押し付けにあるのです。
始めのうちは重大問題が次々に噴出している現代社会とどう関係するのかとお思いになるかもしれませんが、しばらくお付き合い下されば現在直下の問題とも密接に結びついているとおわかりいただけるのではないかと考えております。
なお、後ろの3分の1ほどにはかなり不快感をお持ちになる方もいらっしゃるであろう写真が出てきますので、ご注意ください。

BruceStanfield/iStock
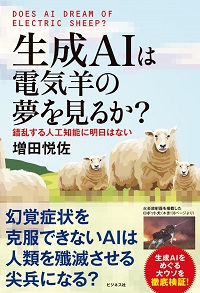
突然語源談議になって恐縮ですが、こうした違和感の根源には日本語ではまったく同じ自由と訳されることばが、英語ではFreedom(形容詞のかたちではFree)とLiberty(形容詞のかたちではLiberal)というまったく違う2つのことばだというところから発しています。
中世ヨーロッパではLiberal Artsと呼ばれて、さまざまな学問の中でもとくに権威が高いとされる学科が7つありました。日本語では自由7学芸などと訳されていますが、なんでも自由な発想でやれるかというと、そんなことはまったくありません。
あれこれめんどくさい決まりごとがあって、きちっとそのとおりにやるのはそうとうな暇人でないと無理というような形式ばった学科ばかりです。私は「暇人の手すさび7芸」とでも訳したほうがいいと思っています。
なぜそんなに堅苦しい約束事ばかりの学問を「自由」と呼んだかというと、生活のために働必要のない自由人にしかできない学問だったからです。では自由人の反対は何かというと、自由人の所有物にされてあくせく働いている奴隷たちということになります。
人間、暇を持て余すと他人の生活に首を突っこんだり、天下国家がどうあるべきかといった話題に嘴を挟んだりしますが、その発祥は生産活動を全部奴隷たちに任せて、暇を持て余していた奴隷主階級のギリシャ人たちだったと思います。
世界全体の人口を極貧生活をしている人たちと、それ以外の人たちの2種類に分けてみましょう。なんと20世紀半ばまで、極貧生活の人たちのほうが多数派だったのです。
.png)
豊かな人たちと貧しい人たちの比率ではありません。極貧生活の人たちと、それよりちょっとマシ程度から大金持ちまで全部との対比なのです。その対比で、1960年になっても極貧生活をしていた人たちのほうが54.1%と多かったのです。
次の、世界1人当たりGDP推計額の推移をご覧になれば、それももっともだと納得していただけるでしょう。
.png) 西暦1年から1800年までの1人当たりGDPもそれなりに上下動はあったのですが、紀元前1000年から西暦2000年までの超長期で見れば、1800年までの動きはX軸からちっとも上がっていないようにしか見えないほど小さな変化でした。
西暦1年から1800年までの1人当たりGDPもそれなりに上下動はあったのですが、紀元前1000年から西暦2000年までの超長期で見れば、1800年までの動きはX軸からちっとも上がっていないようにしか見えないほど小さな変化でした。
ですから、基本的に西暦1800年までは人類全体の9割以上が極貧生活にあえいでいたと言っても過言ではないのです。
動力と言えば家畜と水の流れに頼り、道具と言えばてこの原理と車輪と車軸ぐらいしかなかった時代があまりにも長いこと続いていたので、その間の生産力の伸び方は遅々たるものでした。
そういう中で、王族の数十人だけでなく、王族プラス貴族の数百人でもなく、何千人という階層と呼べる規模の人間集団が暇を持て余していろんなことに口を出す生活ができていたのは、奴隷に仕事をさせていたからこそだというわけです。
つまり、Libertyというのは自由人(=奴隷主)がいろんなことをしたいようにする自由です。一方、Freedomというのはたとえ奴隷の身分でも「死んだり体を壊すほど働かせないでくれ。どうしてもやりたくないことは無理にやらせないでくれ」という拒む自由です。
ちなみに、Freedomのほうの自由はタダ(無料)という概念と密接に関連しています。タダのモノやサービスはだれでも自由に使えるということです。
Give freelyと言えばふだんならおカネを払って買う必要のあるものをタダで差し上げますということですが、Give liberallyと言えば、寄付や募金に多額で応じることです。
Freedomが「何かからの自由」であり、Libertyが「何かへの自由」であることは、アルコールフリーとか、カフェインフリーとかシュガーフリーというのは、アルコールやカフェインや砂糖が入っていないという意味だということからもわかります。
これをアルコールリベラルとかカフェインリベラルとかシュガーリベラルと言ったら、アルコールやカフェインや砂糖がたっぷり入っているという意味になるでしょう。
というわけで、Freedomはどちらかと言えば控えめな自由だと言えます。Libertyが持てる者が現に行使している自由だとすれば、Freedomは持たざる者がいつか行使したいと願っている自由だと言い換えることもできます。
ですが、これが奴隷の立場からご主人様に「Set me free」と言ったとすると、とんでもなくラディカルな要求となります。
どんなに厳格な奴隷制の社会でも、奴隷が自分の才覚でカネを稼いで自分の奴隷としての価値に当たる金額をご主人様に差し出せば、自由人としての身分を買うことができるのがふつうです。
次の小見出しでご紹介しますが、奴隷は非常に高額の商品です。その高額商品がご主人様に「自分をタダで解放してくれ」と言えば、社会秩序の根底にある価格体系を崩してしまいかねない大ごとです。
そうすると、リベラルなご主人様としては「それはちょっと無理だが、お前はなかなか頭もいいし意志も強そうだから、カネ儲けができそうな教育を授けてやろう。それで儲かったら、自由身分を買い取ってくれ」という交渉に入るわけです。
奴隷は貴重な財産だった古い時代にさかのぼるほど定量的なデータが少ないのではっきりした議論はできませんが、古代ギリシャやローマの頃から、奴隷が非常に有利な投資対象だったという定性的な記述はいろいろ残っています。
南北戦争前のアメリカともなると、かなり数量的なデータの蓄積も大きくなるので、奴隷がどのくらい貴重な財産だったか、具体的なことが語れるようになります。
.png)
ご覧のとおり、1770~1850年頃のアメリカでは奴隷は農地に次いで大きな資本で、1年間のGDPの約1.5倍の価値を持っていました。住宅総ストックの約2倍ですから、いかに巨額だったかがわかります。
いったい奴隷ひとりを買うのにいくらぐらいかかったかというと、次のグラフのとおりでした。
.png) 平均価格で言えば住宅1戸とほぼ同額なのに、総額では住宅の約2倍になるのは、住宅は基本的に1世帯1戸、そうとうな大金持ちでも別荘が数ヵ所にあるぐらいなのに、大規模プランテーションでは数百人とか数千人の奴隷を1農園で使役していることも多かったからです。
平均価格で言えば住宅1戸とほぼ同額なのに、総額では住宅の約2倍になるのは、住宅は基本的に1世帯1戸、そうとうな大金持ちでも別荘が数ヵ所にあるぐらいなのに、大規模プランテーションでは数百人とか数千人の奴隷を1農園で使役していることも多かったからです。
奴隷を1人使うと、所有者の「労働」収入がどれだけ増えたかを、今度は名目(つまりその時代時代の時価)ではなく、実質価格で見てみましょう。
.png) 実際には奴隷が働いているのになぜ所有者の労働収入に数えるかというと、奴隷は家畜や機械と同じように人間が使う道具に過ぎない建前になっているからです。
実際には奴隷が働いているのになぜ所有者の労働収入に数えるかというと、奴隷は家畜や機械と同じように人間が使う道具に過ぎない建前になっているからです。
こちらも1850年前後で見ますと、12万ドル前後(現在の米ドルはあまりにも高く評価され過ぎていると思いますが、一応1ドル150円で試算すると1800万円という高額になります)ということで、奴隷がいかに生産性の高い「資本」であったかわかります。










































