国連憲章の文言解釈のレベルでも、「いつでも援用できる」という石破氏の主張には、無理がある。国連憲章第53条の2は、「敵国」の定義を次のように定めている。
敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。 (The term enemy state…applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter.)
第53条の2は、「第二次世界大戦中に連合国として戦っていた諸国の敵陣営にいた枢軸国を永遠に敵国と呼ぶ」と定義しているのではない。「この憲章のいずれかの署名国」にとっての「第二次世界大戦中の敵国」が、憲章が定める「敵国」だ、と言っている。
憲章加盟国と敵国に同時になることはできない、と理解しなければ、日本ですら、国連憲章を署名・批准しているので、第二次世界大戦中の敵国であるアメリカやイギリスやソ連が憲章中の「敵国」である、と主張できることになってしまう。「敵国」は、国連憲章加盟国になった時点で、消滅する。そうでなければ憲章体制が矛盾を抱え込んで崩壊してしまう。
憲章第53条は、第二次世界大戦終結後も直ちに枢軸国に対して「主権平等」原則を適用しなかった過渡期に行われた措置を意識した規定である。そもそも枢軸国に対する占領管理体制が、今日であれば国連憲章第7章の強制措置を発動しなければ行うことができない措置であったため、憲章成立後は論理的整合性を保つための条項が必要だったわけである。
また、1947年英仏条約や1948年西欧五国条約は、「ドイツの再侵略」に対抗する規定を持っていたし、ソ連も東欧諸国と同様の二国間条約を締結していた。それらの条約の法的裏付けが、憲章53条であった。しかしこれらの条約も、いずれも現在では消滅・失効している。
日本は、1941年大西洋憲章の時から自らを「平和愛好国家」と呼ぶことになった「連合国(United Nations)」の「敵国」であったが、その性格を変更するために国家行為で1945年「ポツダム宣言」を受諾して、国家の改変を行った。
広汎に誤解されているが、「ポツダム宣言」受諾で「無条件降伏」をしたのはあくまで日本軍だけであり、日本国は「ポツダム宣言」の内容の履行に責任をもって対応することを約している主体である(十三吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府二対シ要求ス」)。
この「ポツダム宣言」履行義務にしたがって、日本国が、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除」する措置をとり、「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルル」ように、憲法改正などの一連の改革も行った。
連合国は「日本国ノ戦争遂行能力ガ破碎セラレタルコトヲ確証」するために占領を行うが、これはいわば管理監督者の役割なので、「目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ連合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ」という仕組みになっていた。
「目的ガ達成セラレ」たことが確証された瞬間は、1951年「サンフランシスコ講和条約」という形で記録され、占領体制は終結した。この講和条約では、目的達成を確証した評価規準として「国連憲章」が参照されている。
日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し・・・、
連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎する・・・
第五条
(a)日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。
(i)その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。
(ii)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
(iii)国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動又は強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。
(b)連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。
(c)連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
日ソ国交正常化もへて、1956年に実際に日本は国連加盟を果たす。それはつまり、国連憲章を署名・批准し、他の加盟国から、憲章「の義務を履行する能力及び意思があると認められる他のすべての平和愛好国」(国連憲章第4条1項)の一つであることを正式に認めてもらった、ということである。
わかりやすく言えば、日本は第二次世界大戦中に「連合国(United Nations)」の「敵国」だったが、連合国との間に定めた改変手続きを履行して生まれ変わり、「国連(United Nations)」側の仲間の「平和愛好国」になった、ということである。他の国連加盟国/旧連合国は、「日本は敵国だったが、生まれ変わって同じ平和愛好国になったので、憲章2条の『加盟国の主権平等の原則』を適用して『加盟国の地位から生ずる権利及び利益』を全て認めると約束した」、ということなのである。
1995年総会決議で確認されたのは、したがって万が一にも国連加盟国になった日本はもはや「敵国」ではないので(旧敵国の消滅による)、「旧敵国条項は死文化した」という理解に、異議を唱える国は一つもない、という事実である。
それにもかかわらず、日本の衆議院議員・石破茂氏だけは、「日本に敵国条項をいつでも援用することができる」とブログで主張しているのである。
溜息しか出ない。
■
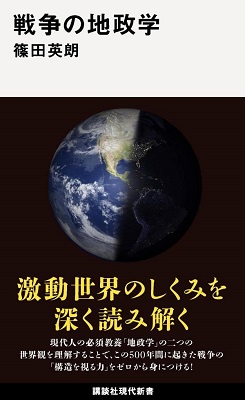
提供元・アゴラ 言論プラットフォーム
【関連記事】
・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」
・大人の発達障害検査をしに行った時の話
・反原発国はオーストリアに続け?
・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』
・強迫的に縁起をかついではいませんか?










































