「くだらない」は、取るに足らないしょうもない物事を指し、人に対しても頻繁に用いられる言葉です。
この「くだらない」という言葉は、江戸時代のお酒から来ているともされています。
そこでここでは、「くだらない」の意味はもちろん、その背景となった語源や由来について解説します。
「くだらない」とは
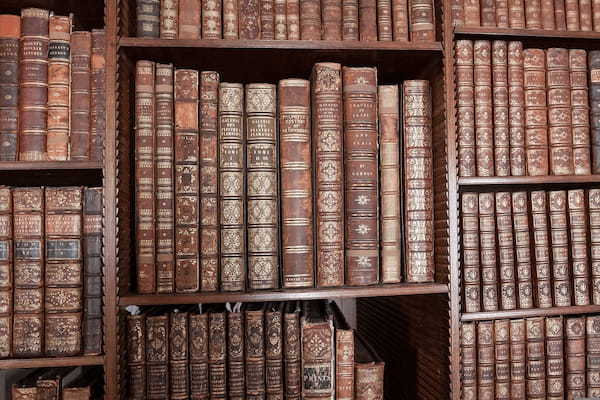
まずは「くだらない」の意味や、対義語について見ていきましょう。
「くだらない」の意味
「くだらない」とは、真面目に取り合うだけの価値がないことをあらわす言葉です。
また、程度が低く馬鹿らしいものを指すこともあります。
その他にも、興を削ぐ様子に対して吐き捨てるように「くだらない」と言葉を発すという用い方がされることもあります。
原則として、ネガティブな表現となります。
「くだらない」の対義語
「くだらない」の対義語としては、「面白い」や「尊い・貴い」などがあげられます。
「面白い」とは、人が興をそそられることをあらわします。
「尊い・貴い」は、崇高で近寄りがたいことを指しています。
極めて価値のあることや貴重なものなどを表す言葉となります。
「くだらない」の語源
「くだらない」は、その語源について諸説あります。
ここでは、由来とされる説を2つご紹介します。
お酒から来たとする説
「くだらない」は、お酒から生まれたとする説があります。
それは江戸時代のことです。
大阪や京都などは、「上方」と呼ばれていました。
この上方の中でも、伏見で醸造されたお酒は質の高い事で知られていました。
そして、伏見を中心に上方で醸造されたお酒は、江戸にも運ばれていました。
江戸の人々は、この上方で作られたお酒を、上方から下ってきた酒という意味で「下り酒」と呼び重宝していました。
対して、関東周辺で作られたお酒は質が落ちるとされました。
そこで、下って来ていないお酒は質が落ちるという意味で「下らない」と表現されるようになりました。
そこから、質の悪いお酒だけではなく、取るに足らない物事についても「くだらない」と表現するようになったとされています。
通じるを意味する「下る」の打ち消し形から来たとする説
動詞としての「下る」には、通じるという意味もあります。
そこに、打ち消しの助動詞「ない」を付けて「くだらない」という表現が生まれたとされます。
「下る」には、もともと「筋が通る」という意味もあります。
その否定形、つまり「筋が通らない」という状態を指す表現として成立したとも考えられています。








































