バングラデシュは独立以来、インドと親密な関係を維持している。しかし中国の経済発展の恩恵も受けており、一帯一路の重要な一角を占める。インドが「クアッド」に加入して、増大する中国の影響力をけん制する動きを「FOIP」の流れの中で進めていくのに刺激され、増大する影響力の行使に余念がない中国に対する警戒心を持ちながら、「バランシング」を心がけて「インド太平洋」を語る。それが「アウトルック(見通し)」という概念を選びとっている経緯でもある(ちなみにASEANもアウトルックという概念を用いながら「インド太平洋」を肯定的に語るので、同じ姿勢だとは言える)。
日本は、日米同盟を外交の基軸とし、「FOIP」の提唱者で推進役だ。米中対立の二極構造の中では、バングラデシュよりも旗幟鮮明に米国寄りである。もともとバングラデシュは、独立以来、非同盟主義の全方位外交を目指しており、立ち位置の違いは今に始まったことではない。それでも両国は親密な関係を保ってきた。数多くの相違にも関わらず、相互理解を図りやすいところもある。
島国として太平洋に浮かぶ日本は、太平洋の対岸に位置する超大国アメリカとの関係を最重要視した外交政策を取り続けている。だからといって中国との地理的な近さが捨象されるわけではない。近年のように中国の国力が日本のそれを凌駕する時代になってくると、日本には日本なりの「バランシング」が必要になっていることは、自明の事柄である。いわば日本は、2つの超大国に対して非対称な「バランシング」をとっている。バングラデシュはより対称性のある「バランシング」を採用しているが、常に必ず完全に中立的であるわけでもない。
つまるところ、超大国にはさまれながら、「バランシング」を余儀なくされている状況を共有する日本とバングラデシュは、お互いの発想方法を理解しあえるところがある。
それをふまえたうえで、バングラデシュの『インド太平洋アウトルック』を見てみよう。まず特筆しなければならないのは、バングラデシュの「国連憲章の諸原則」に対する深いコミットメントだ。これは独立以来の国是であると言ってよい。
日本では、ロシアのウクライナ侵攻をめぐる態度が必ずしも明白ではない諸国があるのは、国際法に対する認識が浅いからだと言わんばかりの言説が見られる。しかし「国連憲章の諸原則」を重視する姿勢では、バングラデシュは真剣である。そもそもバングラデシュという国があるのも、「国連憲章の諸原則」のおかげだ。
日本の言論人の間では、「国連憲章の諸原則に基づく国際秩序」を「リベラルな国際秩序」と呼び変えるアメリカの学者に影響された態度が広範に見受けられる。これは非欧米社会では、間違った態度である。バングラデシュ『IPO』のように、「国連憲章の諸原則に基づく国際秩序」という概念構成を取るのが、正しい。
日本は、「国連憲章の諸原則」の重要性を共有する姿勢をともに確認することによって、バングラデシュとの間の「自由で開かれたインド太平洋」の「価値の共同体」の紐帯を深めたい。それが日本とバングラデシュの国益に合致する。
バングラデシュは、自国の置かれた地政学的環境を鑑みて、ロシア侵略を避難する国連総会決議を棄権し、中国包囲網に関心を持っているかのように見えないようにすることに細心の注意を払うが、「国連憲章の諸原則」を再確認するネットワークとしての「FOIP」とは連携したいと考えている。日本としては、それは素直に受け止め、具体的なパートナーシップ活動につなげたい。
「国際社会の法の支配」のテーマは、実際に4月の岸田・ハシナ首脳会談でも強調された。
そのうえで、バングラデシュとの間で、港湾整備を具体例にして、貿易促進を通じた経済的連携に重きを置くパートナーシップを模索するのは、当然ではある。しかしさらなる具体的な連携のテーマがあるのではないか。
『アウトルック』には、日本とバングラデシュが自然に連携すべきいくつかの政策分野が特記されている。たとえば災害予防・対策である。
バングラデシュは自然災害に悩まされてきた国であり、気候変動の影響も大きく受け始めている。日本は、災害対策で国際的なイニシアチブをとることに強い関心を持ち、太平洋島嶼諸国と災害対策を目的にした国際会議を頻繁に催している。「インド太平洋」の考え方にそって、こうしたイニシアチブを、バングラデシュとも協働して進めていくのは、本来は自然かつ当然の流れであるはずだ。
さらに強調しなければならないのは、バングラデシュが国連PKO要員派遣世界一位の国であり、その実績を『インド太平洋アウトルック』の中でも協調していることだ。日本も国際平和活動への貢献に関心を持っているが、バングラデシュほどの実績はない。バングラデシュの経験に敬意を払いながら、ともにアフリカで能力構築支援などで協力する活動を増やし、ともに国際平和活動への貢献を「FOIP」と結びつける活動を開拓していきたい。
そしてその太平洋の日本とインド洋のバングラデシュが、活動の地理的裾野をアフリカまで広げていくことは、まさに「自由で開かれたインド太平洋」の構想にふさわしい。(もちろん同じことは、インドにも、さらにいっそう強くあてはまるが、バングラデシュとインドは友好関係にあるので、日本がインドとの協働は、日本とバングラデシュとの協働とは競合しない。)
バングラデシュと日本の間に恒常的な制度的関係はない。しかし、ともに「FOIP」を語る「パートナー」とみなしあうだけで十分である。問題は、より具体的な「パートナーシップ」の協働の道筋である。
■
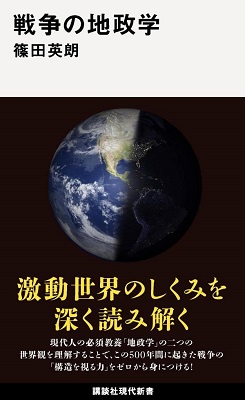
提供元・アゴラ 言論プラットフォーム
【関連記事】
・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」
・大人の発達障害検査をしに行った時の話
・反原発国はオーストリアに続け?
・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』
・強迫的に縁起をかついではいませんか?









































