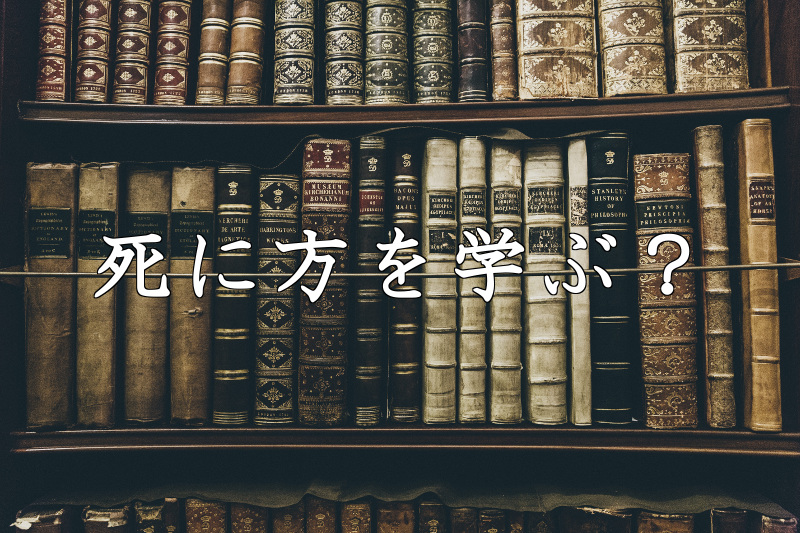
フランスの哲学者・モンテーニュ(1533年-1592年)の『随想録』に、「哲学する目的は、死に方を学ぶことにある」とあります。哲学する目的などというのは、そう簡単に答えられるものではありませんが、之は余りピンとこない言葉に感じられます。私が一つ挙げるとすれば、自分で徐々に死生観を確立して行くということだろうと思います。
死については例えば、マールンクヤという弟子から「霊魂というのは、死後どうなるのですか。不滅なのですか」と聞かれた釈迦が、「苦悩からの解脱こそが最大の重要課題であるにもかかわらず、そのような戯論(けろん)をしていても仕方がない」と諭しています。あるいは、弟子の子路から「死とはどのようなものかお教え下さい」と尋ねられた孔子が、「未だ生を知らず、焉(いずく)んぞ死を知らん…生についてまだ分からないのに、どうして死が分かると言うのだ」と述べています(『論語』)。人間どう深く生きるかが基本で、死のことなど余り考えなくて良い、と私も考えます。
唯、宋の朱新仲が唱え実践した「人生の五計」、「生計…いかに生くべきか/身計…いかに社会に対処していくべきか/家計…いかに家庭を営んでいくべきか/老計…いかに年をとるべきか/死計…いかに死すべきか」、の最後は老計と死計です。「志のある人は、人間は必ず死ぬということを知っている。志のない人は、人間が必ず死ぬということを本当の意味で知らない」とは曹洞宗の開祖・道元禅師の言葉ですが、人間死すべき存在であり何時死ぬか分からぬが故、生を大事にしなければならず、我々は死の覚悟を以て生ある間今ここに、後世に何を残すかということを真剣に考えて行かねばなりません。










































