7月23日に日本維新の会の馬場伸幸代表が、日本共産党について「なくなったらいい政党」といったことが話題になった。
そもそもなくなったらいいと思うのは、言う人の願望だから何も悪いとは思わないが、あたかもドイツのように法律的に禁止すべきだといっているように、問題をすり替えられて必要以上に攻撃されたと思う。
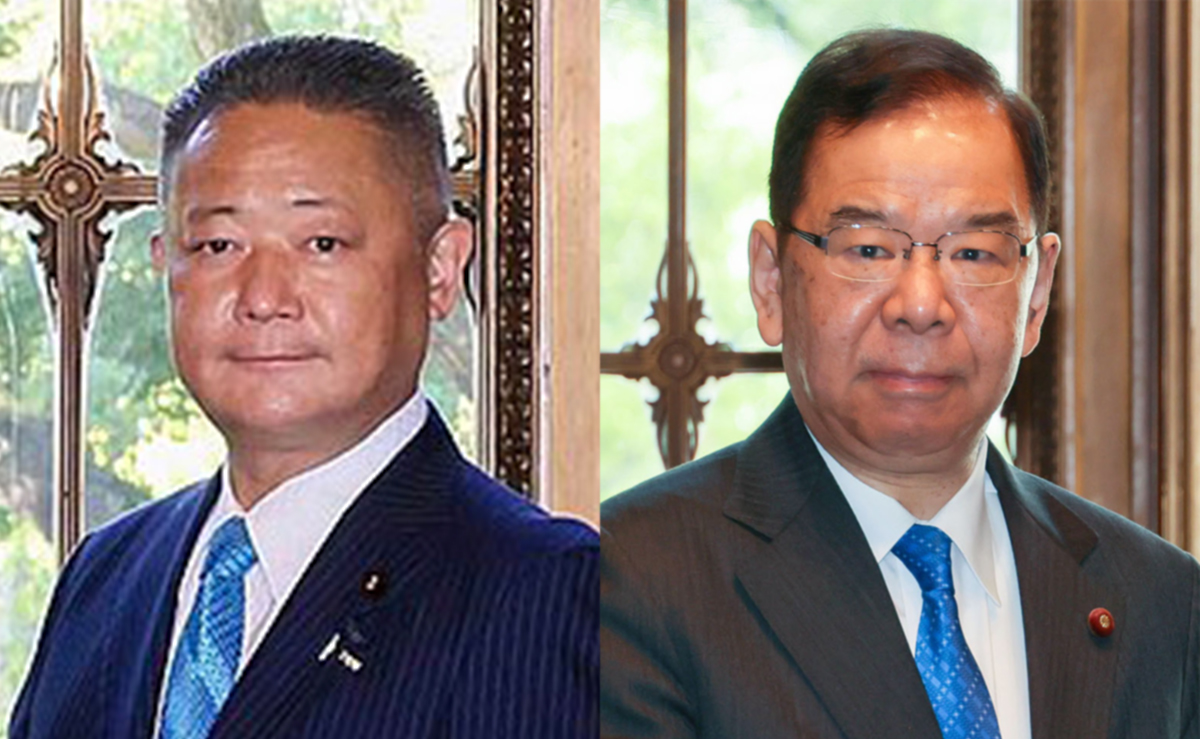
馬場代表と志位委員長 Wikipediaより
私は、ドイツがナチスと共産党を禁止しているのは、歴史的事情があるにせよ、どちらも好ましいとは思わない。ただ、日本の国会で共産党がそこそこの議席をもっているのは、大変恥ずかしいことだと思う。
そして、たまたま、「日本の政治「解体新書」 世襲・反日・宗教・利権、与野党のアキレス腱」(小学館新書)という本で、その点を論じているので、その抜粋を提供しておきたい。
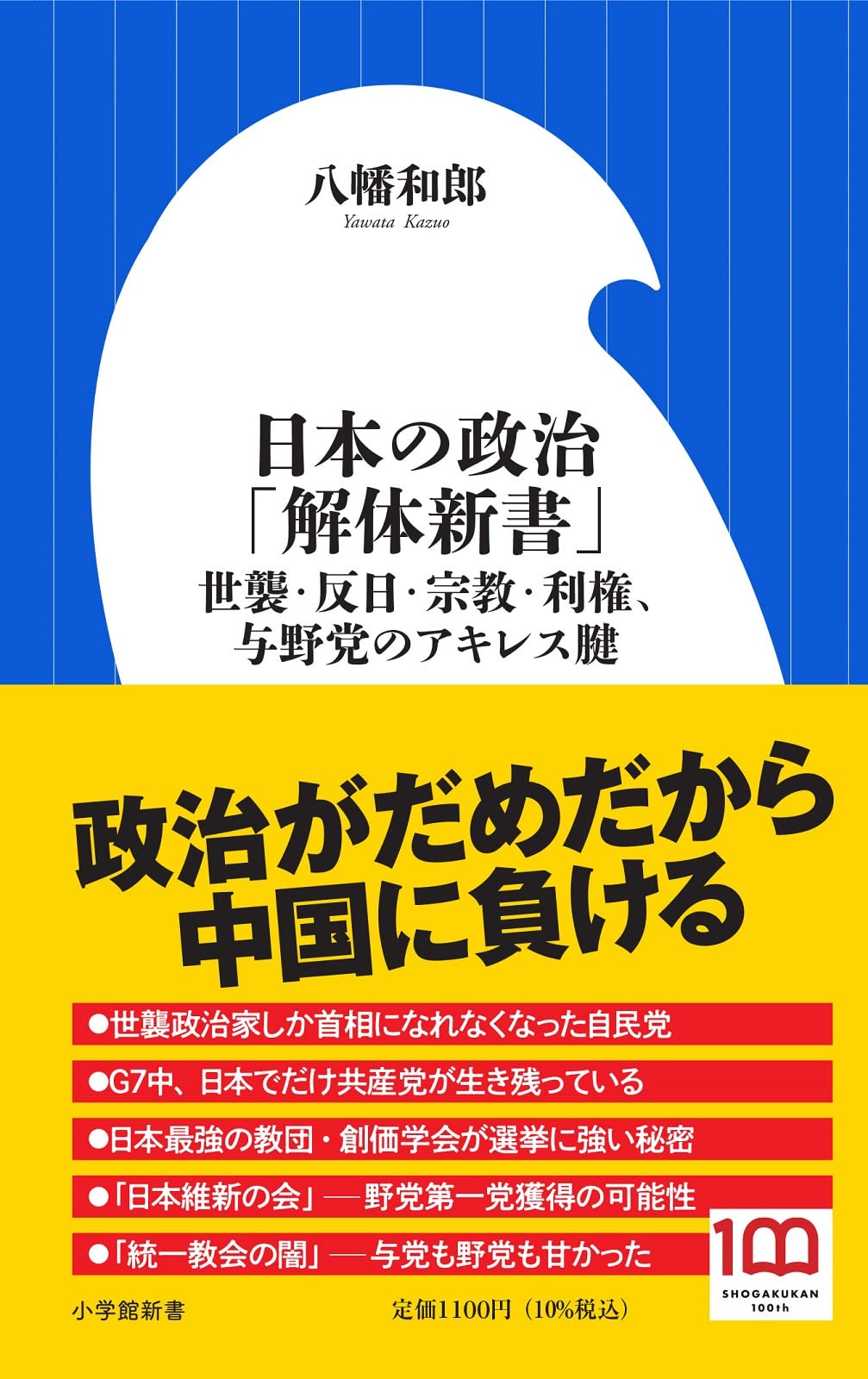
なお、この問題についても、水曜日に行う講演会でも話したいと思う(別添)。
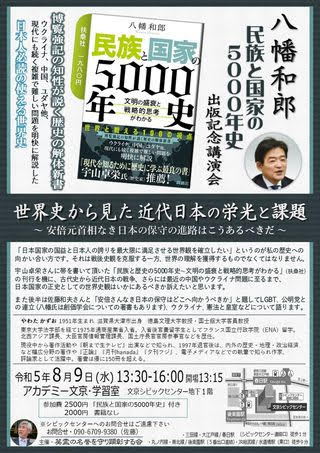
日本の政治地図は保守・革新などでなく、右派と左派という座標軸で得論じられる。日本も英米よりはこちらの方に似ているのだが、まずは、家元ともいえるフランスの政治地図について歴史に沿って紹介しよう。
1789年の革命後の議会で、穏健派が議場の右側、革命派が左側に座ったことから「右翼」「左翼」という言葉が生まれた。その後、君主制に戻ったが、ブルボン家(革命以前の王家)か分家のオルレアン家(1830年~48年の七月王制)か、あるいはボナパルト(ナポレオン)家のどれを担ぐかで議会はいつも争った。
普仏戦争(1871年)のあとの第三共和政の初期には、王党派が右派、共和制を支持するのが左派となる。しかし、間もなく共和制が定着し、フランス革命をもって建国と受け止め、その枠内での保守派と、自由主義者やキリスト教民主主義者(公明党に似ている)などの中間派、そして社会主義者(やがて社会党と共産党に分裂)が、それぞれ右派、中道派、左派と呼ばれるようになり、比例代表制のもとで小党分立になった。
しかし、まだ王党派もいたし、新たに零細業者などを基盤とするポピュリストが台頭して「極右」と呼ばれるようになり、そして無政府主義者などが「極左」と呼ばれるようになった。共産党が極左と呼ばれないのは、こうした経緯があるからだ。
ファシズムが台頭したとき、旧き良きヨーロッパの再興を期待する勢力は好意的で、ドイツ占領下で、ヴィシー政権に多くの既存政治家が参加した。だが、シャルル・ド・ゴール将軍がロンドンから抵抗(レジスタンス)を呼びかけ、ソ連参戦後は共産党員もド・ゴール将軍率いる自由フランスに合流した。
第2次世界大戦後は対独協力派が追放され、共産党を含む挙国一致政府が成立した(共和国臨時政府)。だが、ド・ゴールは強い政府権限を求める意見が通らなかったので下野し、議会で第1党だった共産党も冷戦のあおりで排除され、第四共和政制では中小政党の合従連衡が繰り返され首相は頻繁に交代した。
ところが、アルジェリア独立問題で行き詰まり、1958年に政界から引退していたド・ゴールが復帰して、直接選挙(上位2候補の決選投票)で選ばれる大統領が巨大な権限を持つ第五共和制となった。それを肯定するド・ゴール派が右派の代表となり、権限の制限を要求する中道派や左派と対立したが、ヴァレリー・ジスカール・デスタン(中道派)が74年に、続いてフランソワ・ミッテラン(社会党だが共産党も協力)が81年に大統領となったので、第五共和制は安定した。
議会は比例代表制から小選挙区2回投票に変更され、多くの場合、大統領与党が過半数を占めるが、野党が過半数を占めると、外交・国防は大統領、内政は首相と役割分担する。
その後、EU統合をド・ゴール派(共和党)と社会党が推進し、66年に脱退していたNATOの軍事機構にも09年に復帰するなど、EU統合と西側陣営の一員としての立場を保革両陣営の主流派が支持することになった。









































