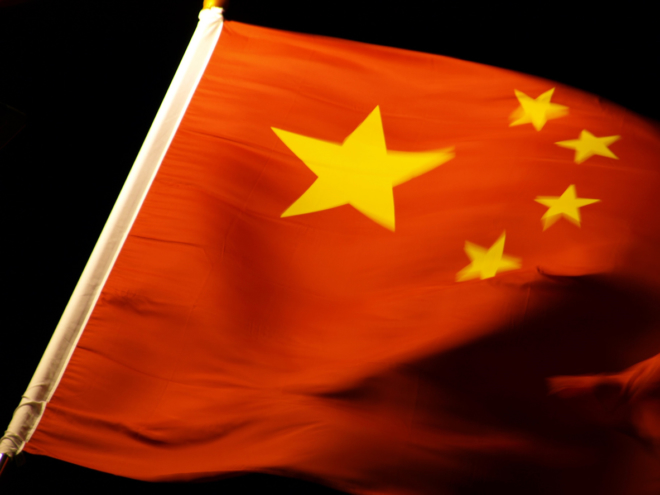
SCM Jeans/iStock
中国経済は瀕死の状態だと、多くの専門家が指摘している。
地方政府の財政破綻、莫大な公共工事による国家財政への圧迫、アメリカをはじめとするデカップリングの流れ、食糧輸入への懸念、若年層の失業率、インフレ率の低下。少し羅列しただけでもこれだけの要素がある。
中国のアキレス腱は、共産主義をベースにした専制政治体制を維持しつつ、資本主義経済を計画経済に取り込んで行くことで、国家ぐるみで巨大な経済圏を作ることが可能な反面、その規模の大きさが裏目に出て、一度歯車が狂い始めるとその反動は計り知れない規模になってしまうことだろう。
分けても、地方経済における信用収縮と財政破綻、ゼロコロナ政策による人流制限が、国内経済の消費を一気に冷え込ませてしまうと同時に、3,000万社とも言われる中小零細企業の活動が止まってしまう。これら、中国経済の屋台骨を支える企業群が止まることは、そのまま国民生活の停滞を意味する。
そもそも、中国が国内消費と国内に還流する人民元の原資としてきたのが、地方行政区のGDPの要ともなる不動産投資だった。中国政府は、上がり続ける不動産価格を背景に、国民の積極投資を促し、国内のインフラ整備や大規模な工場への投資を可能にし、地方銀行の信用創造の元手にしてきた。
そのような中国国内の動きに対して、日本のバブル崩壊のような警戒感を示す諸外国の経済アナリストの声はあったが、大半は膨大な人口、輸出入総額の大きさ、とても国内全てに行き渡ったとは言えないインフラ整備と中国全土への投資が内外から寄せられることで、経済成長はまだまだ続くと考えられてきた。
ところが、アメリカの対中政策の転換により先進国が中国への投資に及び腰になり始めた矢先、コロナ禍が追い打ちをかけることになり、グローバルサプライヤーの見直し、大規模な資本移動の制限、人流の制限等、中国経済にとっては多くの亀裂が生まれる要素が明らかになってきた。更に追い打ちをかけたのが、ロシアのウクライナ侵攻だ。
専制政治体制の国家は、互いに牽制し合いつつ、資本主義国家とのパワーバランスの中にあったのだが、ソヴィエト崩壊以後、社会主義国家、共産主義国家の政治体制では人類理想の社会の実現は不可能であることが明確になってしまった。国家が国民と経済活動と軍事の全てをコントロールすることは不可能なのだ。
社会主義や共産主義の最も間違っているのは、人心をも国家がコントロールするという考え方だ。国家の指導体制に国民を隷属させるためには、厳しい監視体制を敷くしかない。国民一人一人の思想や行動まで国家が制限することは、甚だしい人権蹂躙であり、あってはならないことだ。
巨大な経済規模を背景にしている間は、世界中もその経済力を利用することができただろうが、そもそも、専制政治体制そのものが人類の敵であることは分かりきった話なので、国家が経済力や軍事力を使って他国に影響力を及ぼそうとすれば、強烈な軋轢となり、世界は一気に抵抗感を強くする。










































