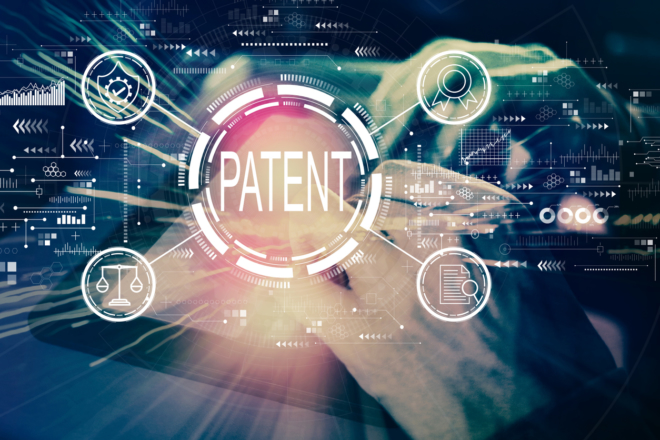
Melpomenem/iStock
先月、産業技術研究所に所属する中国人研究者が逮捕される事件が起きた。研究所が保有する技術情報を中国に持ち出したというのだが、技術情報を元に中国で特許が出願されたのを「中国企業に特許を「横取り」された」と表現した記事が気になった。
秘密性を基準に技術情報は分類できる。学会等を通じて公開される秘密性のない情報と、ノウハウとして組織内に秘匿される情報を左右に置くと、特許に関わる情報は公開情報に近い位置にある。
不思議に思うかもしれないが、技術を公開することで技術のさらなる発展を促す代償に、期限を付けてその技術の独占を認めるのが特許制度だからだ。そのうえ、独占権が行使できるのは、特許権を取得した国に限られる。「横取り」された中国特許が成立したとしても、独占権を行使できるのは中国国内だけだ。仮にわが国に国際出願されても、特許権を与えなければよい。
特許出願情報は多くの国で出願後18か月たつと公開されるようになっている。公開されれば誰でも閲覧できる。これでは技術の秘密は守られない。そこで、公にすることで国家・国⺠の安全を損なう事態が起きる恐れが⼤きい発明に限定して、出願公開等の⼿続を留保する制度ができた。2022年に成立した「経済安全保障推進法」に基づく、秘密特許制度がそれである。









































