
ipopba/iStock
連載第1回で紹介したように、「脱成長」関連作品を始め様々な研究を融合させて、私は「資本主義終焉」後の経済社会システムを「社会資本主義」と命名した。
(前回:「社会資本主義」への途 ①:新しい資本主義のすがた)
留意点は、社会学にも浸透してきた「資本」概念の延伸を受け止めたところにある。その活用を第一義とした「社会資本主義」は、まずは選挙を正しく行う議会制民主主義とグローバル資本主義の骨格を持つ。そのうえで使用範囲を拡張した「資本」概念を取り込みつつ、生活インフラを第一義とする治山治水事業を最優先して、全国的に見て大都市から過疎地までを問わず社会全体で耐久力の限界がせまっている「社会的共通資本」の充足に、「資本」概念を連動させることをねらった。
災害対策にも配慮これには地震や台風や集中豪雨などの災害対策の意義もある。同時に自治体の各種「社会的共通資本」利用を柱として、市民が持つ「社会関係資本」を豊かにすることを目指す。
この両者は、これまでの経済学系の資本主義論では傍流でしかなかったが、社会学の観点からすると、『社会資本主義』を支える極めて重要な概念であるために、ともに活用することにした。
「異次元の少子化対策」にも言及同時に本書では、今後の「人口変容社会」の核を占める少子化の原因と対策について、独自の見解を明らかにした。
「少子化する高齢社会」に関する私の30年間の経験を活かして、「異次元」は「通常次元」の「少子化対策」の見直しから始まると判断して、「通常次元」の諸事業の点検から不要なアウトプットとしての「少子化対策事業」を外す。
なぜなら、少子化対策予算で不要な事業とは、かつて「割れ窓」と称した「タバコ対策促進事業」や「省庁施設のバリアフリー化の推進事業」などかなり多かったからである注1)。このような「人口変容」論も取り込まないと、「新しい資本主義」としての「社会資本主義」は実現しない注2)。
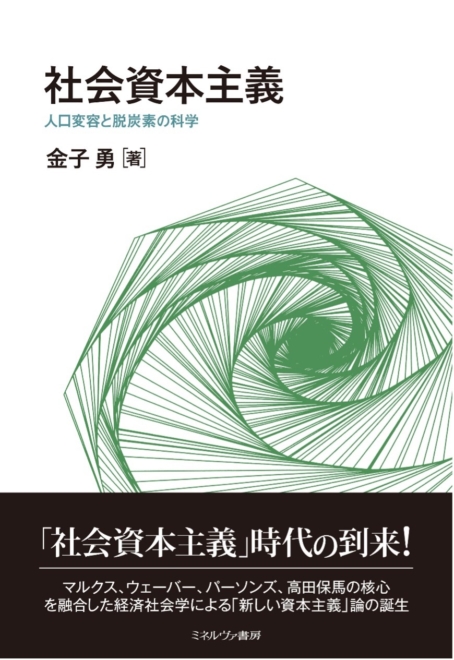
「社会資本主義 – 人口変容と脱炭素の科学」







































