
Satoshi-K/iStock
満員電車に揺られながら長時間の通勤……。
会社に着けば上司からのキツい小言が待っている……。
そんなストレスを抱えながら、会社員として閉塞感を感じている方も多いのではないでしょうか。毎年、GWあたりから、6月のボーナスをもらったくらいに会社の退職を意識して、起業の相談をする人が増えるようです。
「小さな起業を実現してしまえば、会社員としての多くの苦しみから解放されて自由に生きることができます」と語るのは起業コンサルタント(R)、で経営コンサルタント、そして税理士、社労士、行政書士など複数の資格を保有する起業支援のエキスパートである中野裕哲氏。
同氏の監修した書籍「0からわかる!起業超入門」から、さまざまなスタイルで起業する人が増えている現状、起業までの基本ステップ、起業することのメリットについて再構成してお届けします。
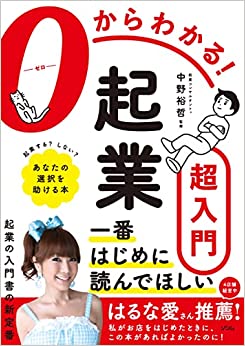
ここ15年ほどで、起業を取り巻く環境は大きく変わりました。最低1千万円の資本金規制が廃止され、極端な話、資本金1円でも株式会社を設立できるようになりました。合同会社という初期費用を抑えられるうえに自由度が高く、仲間同士での起業に向いた会社形態も整備されました。
シェアオフィスを利用すれば家賃や設備投資もほとんどかからず、Facebook、Twitter、InstagramなどのSNSを使えば広告費もほぼゼロ。YouTubeやTikTokを利用すれば、高額なテレビCM公告料を払わずとも、自社の動画を配信することも可能です。
さらにコロナ過を機に広まった在宅ワークやZOOMなどのWeb会議ツールをうまく活用すれば、会議や商談も外出せずにできるし、北海道在住の人が大阪在住の友人、沖縄在住の友人らと3人で会社を作って運営していくという計画でも全く困ることがないと言えます。このように、法律、環境、コスト面などで、駆け出し起業家にとっての追い風が吹く時代になったといえるでしょう。
さらに特質すべきは副業解禁の流れです。以前は規制の厳しかった大企業が副業に対して寛容な姿勢へと切り替えています。背景にあるのは、政府が後押しする働き方改革。個々人が能力をフルに活かして自立的に働く方向へと導く政策を推し進めているのです。企業にとって負担減、個人にとってはリスクヘッジになります。
会社員か起業かの二者択一から、まずは起業を視野に入れつつ副業をしてみるという「第三の選択肢」もできたのです。副業としてミニマムでスタートし、うまくいかなければ会社員1本に戻るもよし。そのまま二足のわらじをはき続けるもよし。
可能性が見えてきた時点で本格的な起業に踏み出すもよし。人生を賭けなくても「おためし」でチャレンジできる環境が整い、慎重派の方々も取りくみやすくなったといえるでしょう。










































