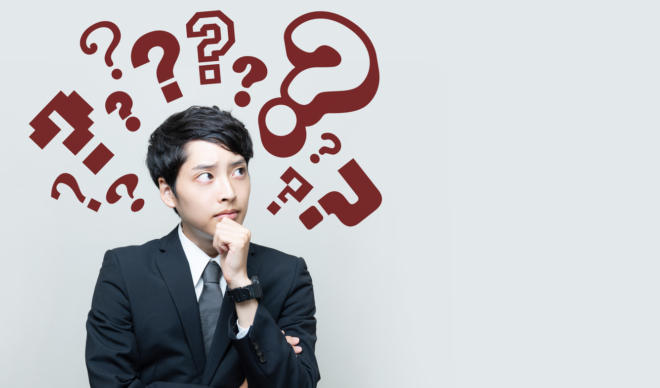
metamorworks/iStock
先日、新人に研修として5日間の一人旅をさせるという会社が話題となりました。
【参考リンク】かわいい“社員”には旅をさせよ
卒業旅行じゃないんだから、と思った人も多いでしょうけど、筆者はなかなか見所のある研修だなと感じましたね。
実は今、新人の育て方が議論となっている日本企業は少なくないです。
ちょっと前に「職場環境がヌルすぎて若手が離職する」という話が話題になりましたが、あれも見方を変えるなら従来の育成方針が時代に沿わなくなっているとも言えるわけですよ。
企業は従来の新人育成にどんな限界を感じているんでしょうか。そして、個人は組織の中で何を目指すべきなんでしょうか。いい機会なのでまとめておきましょう。
従来の新人研修の狙いとはところで、社会人の皆さんは新人研修の内容ってその後の人生で何か役に立ちましたか?「当たり障り無さ過ぎて特に役に立った記憶が無い」「そもそも記憶に残ってない」という人が多いんじゃないでしょうか。
筆者はあまりにも退屈で、「熱が出ました」といってサボった記憶がありますね(汗)
さて、日本企業の新人研修がたいてい薄味なのには理由があります。
日本企業の新卒・総合職採用では、そもそもなんの仕事をさせるかは未定のまま採用の可否のみを判断します。
そりゃ採用担当の頭の隅には何らかの職種に就けるイメージはあるんでしょうけど、建前としては「先発ピッチャーだろうが外野だろうが、会社から与えられた仕事は何でもこなす」のが日本型雇用のルールです。
その後、具体的な配属先が決まるのは入社直前か、新人研修の終了後。時期で言うと5月以降という会社も結構あります。いずれにしても配属は全体の新人研修が終わってからですね。
するとその期間、新人の面倒を見る人事部門としては、営業から総務、技術開発まですべて含めて研修させないといけないわけです。
「誰にとっても当たり障りのない薄味」になってしまうのは必然なんですね。社会人共通のビジネスマナーとか、社史とか理念とか。結構カリキュラム埋めるのが大変だったりしますね。
よく「〇〇社でも採用のマナー講師」みたいな人がメディアに出てたりしますけど、ああいうのはコンテンツとして評価されているわけではないんですよ。
当たり障りのない話で枠を埋めてくれる便利な存在だから、企業の管理部門から重宝がられてるだけなんですね。
じゃあ新人研修なんていらないだろう、4月1日から職場に配属してOJTさせろと思う人も多いかもしれませんが、実際はむしろ「入社式から新人研修までの一連の新入社員イベント」を非常に重視している日本企業の方が多いです。
なぜか。それは、以下のような意識付けを効果的に行える儀式だからです。










































