目次
■ChatGPTがSFXの未来を可能にする?
■インターネットの検索行動の変化とGoogleの対応
Twitter界隈では、ChatGPTの回答クオリティの高さが日々、話題になっている。AIチャットの登場は、今後のインターネットの検索行動にも影響を及ぼすほか、Webビジネスを始めとして、さまざまな仕事にも変化が起きていきそうだ。
AIに仕事が奪われるという現実もすぐそこにある未来。今後、ビジネスはどう変わっていき、どう活用すべきだろうか。AIチャットについてTwitterで発信している、SEO(検索エンジン最適化)の専門家でエンジニアの柏崎剛さんにAIの今後を予測してもらった。
【取材協力:柏崎 剛】
株式会社コンテンシャル代表/1979年、東京都生まれ。インターネットにおけるマーケティングやクリエイティブに携わるプロジェクトや開発に参画し、SEOのコンサルティングとして活動。得意な領域は美容医療系・教育系・ITテクノロジー系・アフィリエイトメディア全般。「再検索キーワード調査」「共起語調査ツール」などのSEOツールを無料で公開している。TwitterでGPTまわりのことをつぶやく、“AIおじさん”としても話題。著書に『目からウロコのSEO対策「真」常識』(幻冬舎)がある。
■ChatGPTがSFXの未来を可能にする?
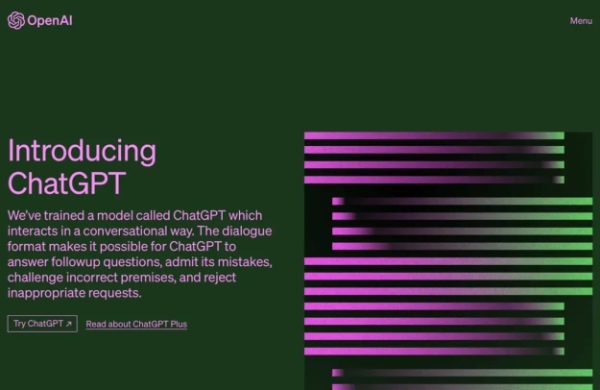
“AIの進化なんてまだ先のこと”として高をくくっていたが、ChatGPTの登場はそれをくつがえしそうな勢いがある。そもそも、ChatGPTの何がそこまで驚異なのだろうか?
「ChatGPTは、アメリカのOpen AIというイーロン・マスクらによる会社が開発した自然な対話を生成することができるAIです。Open AIは設立当初、非営利の研究機関でしたが、2019年にMicrosoftと提携して資金を得たことで開発が加速し、2020年7月にGPT-3が公開されました。これが膨大な量のテキストデータを学習し始めたことで専門機関やエンジニア業界に大きなインパクトを与えたのです。そして、2022年11月に進化系であるGPT-3.5が搭載されたChatGPTが公開されました。
ChatGPTの何がすごいかというと、誰でもログインして質問すれば返してくれるところ。そのチャット型のインターフェイスが使いやすく、後ろに人がいるのかと思うくらい自然な文章で返してくれるのがとんでもないと話題になっています。さらにアクティブユーザー数が1億人を達成するまでにかかった時間は史上最速の2カ月。TikTokとInstagramがそれぞれ9カ月と2年半かかったことからも、そのすごさがわかります」(柏崎さん、以下同)
ChatGPTのすぐれた性能はさまざまな分野に発揮される。論文などはテーマを与えられると自然な文章となって作成されることからニューヨーク市では学校内のシステムやネットワークでChatGTPの使用を禁止したほど。このほか、コンピューターのプログラミングやバグの解消、数学や物理の問題を解く、翻訳、アイデア出しなどは得意分野。逆に現時点では、情報が正確でなかったり、学習しているデータが最新でない(2021年9月まで)、ローカル情報には対応していないなどが苦手分野となっている。
そして3月14日には、GPT-3.5の後継となるGPT-4がリリースされた。リリースされるたびに進化が著しいが、今回のアップグレードもすごい。アメリカの司法試験の模擬テストを受けさせたところ、GPT-3.5では不合格となっていた能力が、GPT-4においては上位10%程度の成績で合格するという驚異的な進化を遂げたという。
「GPT-4は、GTP-3と比較してマルチモーダルモデルとなった他、パラメーター数、最大トークン(記憶力のようなもの)といった部分が大幅に強化されました。近いうちに、出力も文字データだけではなく音声や動力と連動してくることは間違いないと思います。肉声でロボットに問い合わせや指示を行う会話型のコミュニケーションは、さながらSFX映画のような世界です」
■インターネットの検索行動の変化とGoogleの対応
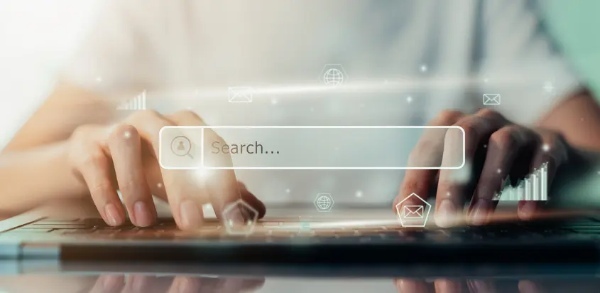
質問するだけで秀逸な回答が返ってくるなら、調べ物をするためにインターネットで検索していた行動も変わっていきそうだ。
「そうですね。私たちが調べ物をするときに検索を続けるかどうかは疑問視しています。昨今では、TikTokとInstagramというような”流し見”で済んでしまうプル型のコンテンツやプラットフォームが爆発的な人気を誇っています。検索はWebサイトを一覧で紹介する機能なので、コンテンツを自ら閲覧し、埋もれている情報を探さなければならない点で労力がかかります。これをすっ飛ばして対話型で答えのみを情報提供してくるのがAIであるため、検索エンジンよりも効率的な部分があります」
とはいえ、検索行動がすぐに変わってくるものでもないというのも柏崎さんの見解。その理由は検索とAIが共存するようなインターフェイスになるからと予測する。
「検索エンジンといえばGoogleが圧倒的なシェアですが、それに次ぐBingというMicrosoftの検索エンジンがGPTを検索に入れてきました。検索窓に入力するとAIが応答するしくみをつくってきたのです。つまり私たちが検索しようと思っても、知らず知らずの間にAIを使っている場合もあるということ。ハイブリッドで共存するようなものになっていく可能性があります」
そうなると、これまでインターネットの世界で強大な影響力をもってきたGoogleはどのようになっていくのだろうか?
「実際にGoogleはコードレッド(非常事態)を宣言したことが有名です。この1月にレイオフしたことも関係しているかもしれません。後発となったもののGoogleもチャットAIの『Bard』を発表し、検索エンジンに対話型AIとして組み込んだ形で試験運用が開始されており、今後は順次利用可能となるようです。また、3月14日には大規模言語モデルの『PaLM』を発表し、既にGoogle CloudなどのAPIで開放するなどして、先行するMicrosoftを猛追しています。今のところ精度、話題性ともにChatGPTに分があるという見方でしたが、『PaLM』は性能に値するニューラルネットワークの規模が、現時点でGPTを上回っているとのことで期待が持てるでしょう。どちらにしても、Googleは『AIの波には逆らえない』として、コードレッド宣言を行ったと考えられるので、検索エンジンは維持しつつも、引き続きAIチャットボットの開発に力を入れてくると考えています」









































