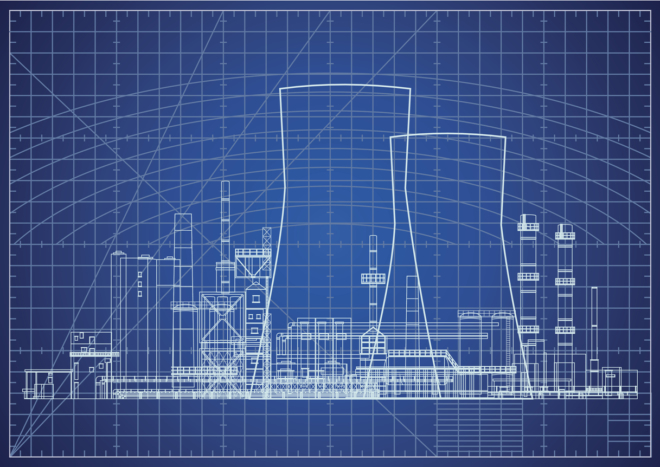
Youst/iStock
政策提言委員・経済安全保障マネジメント支援機構上席研究員 藤谷 昌敏
2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻は、世界規模でのエネルギー危機を引き起こした。今、世界は、気候変動の原因となるCO2を減らす脱炭素と必要なエネルギーを合理的な価格で継続的に確保するエネルギー安全保障をいかに両立させるかが大きな課題となっている。
エネルギー安全保障の観点からも、日本は官民あげて、エネルギー自給率を向上させなければならない。ちなみに2021年の日本のエネルギー自給率は約11%にとどまっており、米国の106%など諸外国に比べて圧倒的に自給率が低い。
経済産業省によると、2021年の時点で日本は石油の輸入量の4%、天然ガスの9%、石炭の11%をロシアに依存していた。これは、欧州諸国の中でもドイツが2020年に石油34%、天然ガス43%、石炭48%をロシアに依存していたことと比べると低い数値だが、日本のエネルギー自給率の低さを考えれば、ウクライナ侵攻の影響は決して小さくないと言える。
このような中、日本国内では近年の異常天候の影響で異例の暑さが続き、電力需給が恒常的にひっ迫するようになった。こうした事態を受けて、昨年末、日本政府は原発の再稼働の追加及び、原発の新規建設も検討することを明らかにした。
原発の再稼働と新規建設は、脱炭素社会の実現とエネルギーの自給という2つの課題の両方を同時に解決する手段だが、原子炉の安全性という問題がどうしても付きまとうことも事実だ。今、政府は、こうした問題を解決するために効率性や安全性を向上させた革新原子炉を開発しようとしているが、それはどのようなものなのだろうか。










































