
ノーベル経済学賞受賞者のダニエル・カーネマン氏が言うように、「私たちにはパターンを探そうとする傾向があり、世界には一貫性があると信じている…実際には因果関係が存在しなくても、原因と結果を仕立て上げるのも得意技である」ということです(ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー(上)』早川書房、2014年、194、205頁)。
こうした直観的思考は、認知心理学では「システム1」と言います。このシステム1は、我々に軍備拡張が戦争を引き起こしていると告げるのです。
軍拡戦争原因論を唱えた著名な評論家として、加藤周一氏がいます。かれはこう主張しています。
戦争の準備をすれば、戦争になる確率が大きい。もし平和を望むなら戦争を準備せよじゃない。平和を望むならば、平和を準備した方がいい。戦争を準備しないほうがいいです。準備は容易に本当の戦争の方へ近づいていく。非常に早く強く。
要するに、加藤氏は、国家が軍備を強化すれば戦争を引き起こす、国家が軍備を備えなければ戦争は起こらないということです。確かに、戦争の前には必ずと言ってよいほど、対立する国家間で軍備拡張競争が発生します。よって、軍拡競争が戦争を招いていると考えても、人間の認知機能のシステム1から判断するのであれば、決して不思議なことではありません。
ところが、こうしたもっともらしい「俗説」に強い異議を唱える政治学者がいます。ブルース・ブエノ・デ・メスキータ氏(ニューヨーク大学)です。彼は計量アプローチによる政治研究を得意としており、戦争メカニズムの解明や政治指導者の行動分析で世界中の学者から注目されてきました。
人間の脳機能には、先に述べた直観による判断の「システム1」の他に、熟慮する「システム2」があります。ブエノ・デ・メスキータ氏は、この「システム2」を使って軍拡と戦争を考えると、「俗説」がおかしいことに気づくはずだと以下のように述べています。少し長い引用になりますが、お付き合いください。
軍拡競争が戦争を引き起こす、と多くの者が信じている…ある国家が軍備を増強すれば、その敵対国は安全を脅かされたと恐れる。そこで、国防のため、自らを護ろうとする。こうして軍拡競争は最終的に、とてつもなく過剰な殺人、破壊力を生み出すことになる。アメリカとソ連の核兵器で地球を何度、破壊できるか、思い出してほしい!そこで、兵器レベルが国防の域を大きく超えてしまい、手に負えない状態になり、戦争がはじまる。
(『ゲーム理論で不幸な未来が変わる!』徳間書店、2010年、74ページ)。
これがよくある軍拡が戦争を引き起こす推論のパターンでしょう。彼は続けて、こう読者に訴えます。
ちょっとまった、落ち着いて、よく考えてみよう。この論法だと、つまるところ、戦争をした場合の代償がとてつもなく高くなっているときに、戦争が起こりやすくなる、ということになる。これはおかしい。人間はふつう高いものはあまり買わない、というのが常識であり経済学の基本である。その逆ではないのだ。戦争だけ逆ということはないだろう。たしかに、戦争が起こる場合、ほぼ例外なく、その前に軍備の増強がおこなわれる。だが、これはいま話している軍拡競争の問題とは関係ない…わたしたちがいま知りたいのは、戦争の前に兵器が購入されることはよくあるのかということではなく、兵器の大量獲得が戦争の原因となることはよくあるのか、ということである。そして、それへの答えは「めったにない」だ(同書、74ー75ページ)。
つまり、軍拡と戦争はほとんどのケースで因果関係(軍拡=原因、戦争=結果)にないということです。そうではなく、たいてい両者は相関関係(軍拡⇔戦争)なのです。
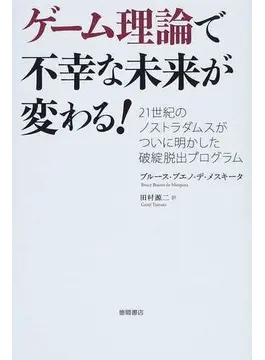
大半の戦略研究者が同意するように、戦争は国家の指導者が合理的に行動した結果として起こると説明できます。ブエノ・デ・メスキータ氏は、戦争研究で頻繁に引用される高著『戦争の罠(The War Trap)』(イェール大学出版局、1981年)において、ウィーン会議以降の58件の国家間戦争では、戦闘を開始した国が42回の勝利を収めていると述べています(同書、21-22ページ)。
エヴァン・ルアード氏(オックスフォード大学)は、1400年以後の戦争を社会学の視点から総合的に研究した著作『国際社会における戦争―国際社会学の研究―(War in International Society)』(イェール大学出版局、1986年)において、「開戦国が戦争に負けた、いかなる場合でも、そこには誤算があった。(開戦国は)勝利するだろうと考えたから戦争を始めたのだ」と断言しています(同書、232ページ)。
これらのデータは、誤算はあれども、戦争は国家による合理的決定の産物であることを支持しています。
こうした戦争研究は、戦争が起こりやすい条件と起こりにくい条件を明確にしてくれます。すなわち、戦争は、国家にとって、そのコストが高くなればなるほど生起しにくくなる反面、そのコストが低くなればなるほど発生しやすくなるのです。
それでは軍備拡張競争は、戦争のコストを上昇させるのでしょうか、それとも減少させるのでしょうか。答えは自明です。軍拡は戦争を高くつくものにするのです。そうであれば、我々の直観に反して、軍拡は戦争を起こしにくくする反面、軍縮は戦争を起こしやすくすると論理的に推論できるのです。このことをブエノ・デ・メスキータ氏は以下のように説明しています。
これまでの戦争に目をやり、その前に軍拡競争があったのではないかと問うのは、原因と結果を混同しているということになる。予想される破壊があまりにも大きいという、まさにその理由だけで、戦争が回避されることもあるのだ、軍備が戦争を抑止するということである。その例はたくさんあるのに、わたしたちはついそれを無視してしまう。大戦争がまれなのは、戦争があまりにも高くつくとき、わたしたちは妥協する道を探すからである。だから、たとえば、1962年のキューバ・ミサイル危機は平和裏に幕を閉じた。冷戦期間中の米ソ間の大きな危機がことごとく、武力戦にいたらずに終わったのも、同じ理由からだ…したがって、とくに平和時には、因果関係の逆転がよく起こる。政策決定者たちが、世界をより平和にしようと、熱心に軍縮交渉に取り組むというのは、彼らが気づいているよりもずっと大きなリスクを抱え込むことなのである(同書、75-76ページ)。
我々の認知メカニズムには厄介なものがあります。それは「講釈の誤り」(ニコラス・タレブ氏)や「確証バイアス」と呼ばれる、過去の出来事を解明しようとする際に冒しがちな過ちです。
このことをカーネマン氏は、こう指摘しています。「起こらなかった無数の事象よりも、たまたま起きた衝撃的な事象に注意を向ける…目立つ出来事は、因果関係をでっちあげる後講釈の題材になりやすい…人間の脳は、平凡な出来事、目立たない出来事は見落とすようにできている」と(『ファスト&スロー(上)』349、351ページ)。
だから、我々は大戦争になった数少ない事象は強烈に認識する一方で、戦争にならなかった数多くの対立や危機は見過ごしてしまうのです。そして軍拡の後に起こった戦争の強い印象から、両者の間に因果関係を作り上げる反面、軍拡があったにもかかわらず戦争にならなかった現象を見逃すのです。
吠えなかった犬アーサー・コナン・ドイル氏の推理小説に登場するシャーロック・ホームズの「吠えなかった犬の推理」は、ご存じの方も多いでしょう。名馬である白銀号が失踪するという事件の解明を依頼されたホームズは、ある起こらなかったことに着目して、犯人を突き止めます。それは事件があった夜に、番犬が吠えなかったことでした。不審者が忍び込めば番犬は吠えるはずなのに吠えなかったということは、犯人は顔見知りの人間であるということです。
これと同じような「推理」は、戦争の原因を推論する際にも役に立ちます。戦争が起こってもおかしくないのに、起こらなかった事例を調べると、その原因が見えてくるのです。
軍備競争が戦争の原因ならば、米ソが激しく争っていた冷戦期に、何度も大きな戦争が発生していたでしょう。しかしながら、近代国際政治において最も激しい軍備拡張競争を行ったアメリカとソ連は、ただの一度も戦火を交えていないのです。冷戦史の大家であるジョン・ルイス・ギャディス氏(イェール大学)は、歴史の反実仮想を用いて、以下のように分析しています。
1945年以降の超大国の政治家が、それ以前の政治家に比べて、互いに戦争の危険を冒すことにとりわけ慎重であることは認めなければならない、この点を検討するには、1945年以降の米ソ関係における危機のリストを一瞥すればよい。イラン(1946年)、ギリシャ(1947年)、ベルリンとチェコスロバキア(1948年)、朝鮮(1950年)、東ベルリン暴動(1953年)、ハンガリー動乱(1956年)、二度目のベルリン危機(1958~59年)、U-2機撃墜事件(1960年)、三度目のベルリン危機(1961年)、キューバ・ミサイル危機(1962年)、チェコスロバキア(1968年)、ヨム・キプール戦争(1973年)、アフガニスタン(1979年)、ポーランド(1981年)、大韓航空機撃墜事件(1983年)——どれほど多くの危機が米ソ関係に振りかかったことか、これが他の時代、他の敵対国間のことであれば、遅かれ早かれ戦争になっていたであろう。
(『ロング・ピース』芦書房、2002年〔原著1987年〕、395-396ページ)
これらの危機や事件が戦争にならなかったのは、偶然にしては、その数が多すぎます。それでは、冷戦期の米ソの指導者が特別に平和愛好者だったのでしょうか。この仮説を裏づける歴史証拠は1つもありませんし、そのように考えるのはあまりにナイーブでしょう。要するに、米ソは強力な核兵器という軍備を持ってしまったために、それが使用される戦争はあまりに高くつくので、できなくなったということです。
この記事を読んで、イランやギリシャといった事例は、ソ連が核実験をする前のことではないかと反論される方がおられるかもしれません。確かに、アメリカは核兵器を独占していた時に、ソ連の核保有を阻止する軍事オプションを検討しました。
しかしながら、ワシントンの結論は、ソ連の核施設を攻撃することは、同国と全面戦争することを覚悟しなければならないために、あまりにリスクとコストが高すぎて、実行できないということでした(Alexandre Debs and Nuno P. Monteiro, Nuclear Politics: The Strategic Causes of Proliferation, Cambridge University Press, 2016参照)。
国家間の軍備拡張競争は、たいてい戦争の原因ではなく、むしろ戦争を抑制する効果があるのです。なお、軍拡と戦争の関係については、21世紀に入り、政治学者による研究が進んだことにより、軍拡が国家の安全保障にとって最適であるケースとそうでないケースが明らかにされてきました。これについては、あらためて別の機会に解説します。 戦争原因論の古典的著作を執筆したジェフリー・ブレイニー氏は、国家の指導者に戦争への楽観主義を戒めるものが平和の原因になると喝破しました。敵国が武力を強化していることを見た政治家は、戦争をしても簡単には勝てないだろうと判断するでしょう。このように軍備拡張は現状打破国に戦争を思いとどまらせるよう作用するのです。
この記事の最初の方で引用した加藤氏の発言は、他の条件が等しければ、「戦争の準備をすれば、戦争になる確率が低い。もし平和を望むなら戦争を準備せよ」と言い換えなければならないでしょう。ラテン語の格言「汝平和を欲せば、戦争に備えよ」は、政治学の主要な戦争研究に裏づけられるものなのです。













































