昨年12月16日、政府はいわゆる「安保3文書」を閣議決定した。新たな「国家安全保障戦略」は「相手からミサイルによる攻撃がなされた場合、ミサイル防衛網により、飛来するミサイルを防ぎつつ、相手からの更なる武力攻撃を防ぐために、我が国から有効な反撃を相手に加える能力、すなわち反撃能力を保有する必要がある」と明記した。
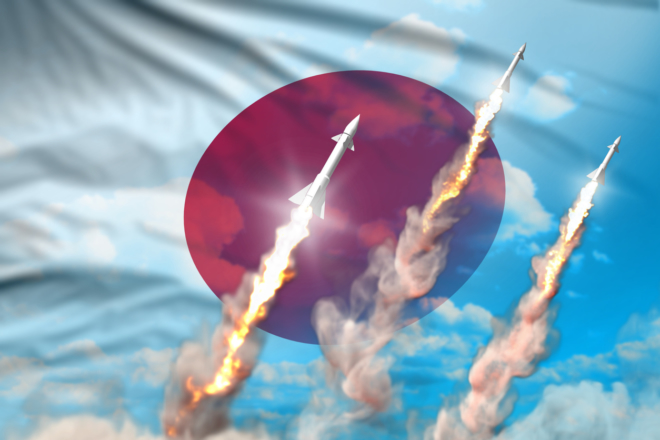
DancingMan/iStock
詳しくは月刊「正論」3月号の拙稿に委ねるが、私に言わせれば、「反撃能力」という命名から不適切なうえに、説明も不正確。正しくは「相手からミサイルによる攻撃がなされた場合」ではなく、「攻撃がなされる場合」である。
国連憲章が自衛権行使の要件とした「武力攻撃が発生した場合」の英文(正文)は「if an armed attack occurs」である。いわゆる「3単現のs」が示すとおり、時制に着目し、正確に翻訳すれば、「武力攻撃が発生した場合」ではなく「武力攻撃が発生する場合」となる。それが「反撃」であれ、「敵基地攻撃」であれ、国際法上許された自衛権を行使できる要件は、世界共通「武力攻撃が発生する場合」である。
通説的な国際法学者の説明を借りれば、「核ミサイル攻撃でも、相手国のミサイル弾基地に攻撃が命令されたときに『武力攻撃』は存在するにいたっている」(高野雄一『国際法概論』弘文堂)。ミサイルが着弾し「すでに日本の国土や人間に被害が発生している」必要はない(同前)。
そもそも国際法上「反撃」など許されない。国連憲章は復仇権の留保を認めていない。「他国の武力攻撃がすんでしまった段階では、たとい自国の艦船、航空機に損害が生じていたとしても、自衛の行動はとりえない」(前掲高野)。
そう繰り返し、メディアで説いてきたが、筆力乏しく、いまだ理解が広まっていない。それどころか、以下のとおり、致命的な誤解が現場の最前線にも及んでいる。
去る2月3日付「朝日新聞」朝刊にインタビュー記事「(交論)専守防衛どこへ 林吉永さん、冷泉彰彦さん」が掲載された。後者は無視し、前者に焦点を絞ろう。記事タイトルは「引き金引くな、歴史繰り返さぬ 林吉永さん(元航空自衛隊第7航空団司令)」。なかで、こう語る。













































