お昼の正午の語源でもある
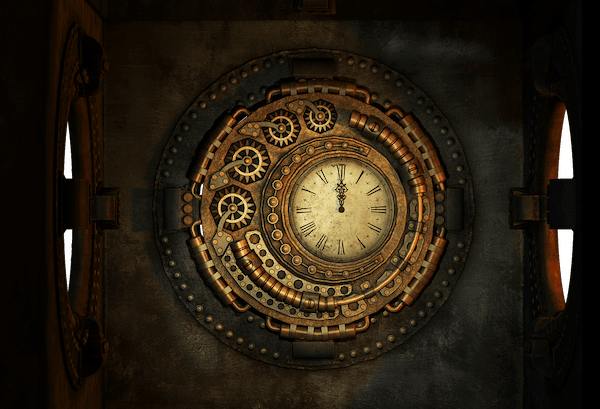
(画像=『FUNDO』より 引用)
十二時辰を語源とする言葉には、現在も使われているものもあります。
一番有名なのが、お昼を指す「正午」です。
正子(しょうし)と正午(しょうご)
「正午」の語源は、午の刻の正刻です。
既にお話したように、時辰の真ん中の時間を「正刻」と呼びます。
深夜の0時を子の刻の正刻として「正子」と呼ぶというのは前述のとおりです。
それと同じように昼12時を示す午の刻の正刻を「正午」と呼ぶのです。
昔の時間は一定じゃない?

(画像=『FUNDO』より 引用)
ここまで解説してきた十二時辰ですが、実は当時の時間は現代のように一定ではなかったんだとか!?
不定時法を採用していた
当時の日本では、日の出や日の入りを基準とした不定時法を採用していました。
不定時法とは、昼と夜をそれぞれ6等分し、6等分に分けた刻に干支を配置しました。
そのため、今のように時間が一定ではなかったのです。
夏の昼は長く冬の昼は短い
日の長さは、季節によって変わってくるものです。
夏場は日の入りが遅く、冬場は日がすぐに落ちてしまいます。
そのため、一刻の時間は夏の昼はやや長く、冬の昼はやや短かったのだそうです。
例:ある冬の一日
日の出が6:30で日の入りが16:30の場合、
日中の時間は6:30~16:30の10時間
夜の時間は16:30~6:30の14時間となります。
不定時法の場合、昼夜をそれぞれ6等分した時間を1刻としますので日中は10時間を6等分し、一刻が100分となります。
夜は14時間を6等分し、一刻は140分となります。













































