魚には、大きく分けて赤身魚と白身魚があります。
これは文字通り、その身の色によって区別されています。
この2つの魚の違いは、泳ぎ方とその泳ぎ方を支える成分にあるのだとか。
そこでここでは、赤身魚と白身魚の違いについて見ていきましょう。
どのような成分により、魚の身は赤くなったり白くなるのでしょうか。
「赤身魚」と「白身魚」

魚の分類には、無数の分け方があります。
そこで、食材として使われる魚の分類を考えてみましょう。
それだと、赤身魚と白身魚という分け方をすることが多いのではないでしょうか。
では、どのような魚が赤身魚で、どのような魚が白身魚なのでしょうか?
代表的な「赤身魚」と「白身魚」
ここからは、まず代表的な赤身魚と白身魚をご紹介します。
代表的な赤身魚

代表的な赤身魚としてはマグロやカツオ、ブリ、アジ、イワシ、サンマ、サバなどがいます。
これらの魚はさばいた際に身が赤いことで、文字通り「赤い身をしている魚」として分類されています。
ただし、一部の魚は青魚という呼ばれ方をします。
とはいえ、青魚などの呼称については身の色合いから来たものではありません。
体の表面の色合いから来ている名前となっています。
代表的な白身魚

代表的な白身魚としてはマダイやヒラメ、カレイ、タラ、フグ、アナゴなどがいます。
これらの魚を捌くとその身は白く、文字通り「白い身をしている魚」となります。
「赤身魚」と「白身魚」の成分の違い
では、なぜ同じ海に生息する魚たちの中で、赤身魚と白身魚がいるのでしょうか?
これは成分の違いがあるためだとされています。
ヘモグロビンやミオグロビンなどの「色素タンパク質」の量の違いによって、魚の身は色が変わるのです。
ヘモグロビンやミオグロビンは、赤身魚の場合、筋肉100g中に150mgほど含有しています。
それに対して白身魚は、10mg以下となっていることが多いです。
「赤身魚」と「白身魚」の泳ぎ方
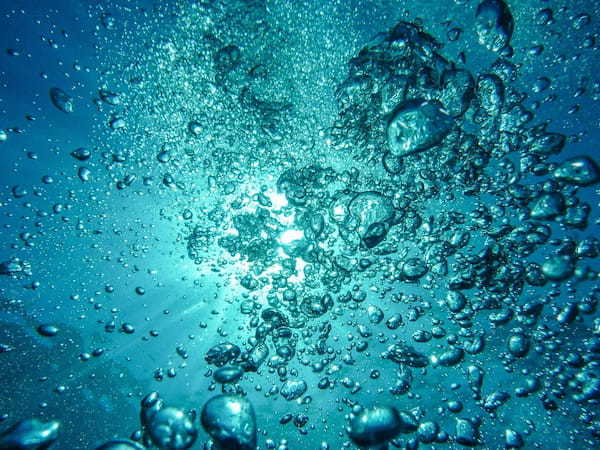
赤身魚と白身魚には、泳ぎ方の違いもあります。
それによって体内のヘモグロビンやミオグロビンを必要とする量も変わるのです。
それが赤や白という身の色に影響を与えているとされています。
「赤身魚」の場合
マグロやカツオなどの赤身魚は、常に泳ぎ続ける回遊性の魚です。
それに必要なのが長時間動かすことのできる筋肉の「遅筋」となります。
この遅筋は、人間でいうマラソンなど継続的な動きをするのに必要な筋肉とされています。
この遅筋、使うには多くの酸素を必要とします。
それを助けてくれるのが、ヘモグロビンやミオグロビンです。
これら「色素タンパク質」は、酸素を貯蔵してくれる効果があります。
すると自然と遅筋を使う魚はそれらの成分が多くなります。
より多くのヘモグロビンやミオグロビンを必要とするからこそ、回遊性の魚の身は赤くなる傾向にあるのです。
「白身魚」の場合
マダイやヒラメなどの白身魚は、海底でじっとする滞留性の魚です。
瞬発的な泳ぎの方を重視しており、人間でいうダッシュやジャンプと言った無酸素運動で用いる筋肉「速筋」が使われます。
そのため、ヘモグロビンやミオグロビンは必要としません。
それゆえに、白身魚の身は赤くならず、白いとされています。













































