僕は、9年間日立製作所(旧)エネルギー研究所にて沸騰水型原子力発電の核燃料の研究開発に従事し、その間、論文博士として九州大学からも博士号を授与していただきました。その後いまから23年前の1999年に、クイーンズランド大学で金属材料工学の博士研究員として人生を再出発して以降、軽金属合金の鋳造凝固、水素吸蔵合金や鉛フリーハンダの研究と材料工学の講義を生業としています。
というわけで、材料工学者として、教育者としては、僕自身は気候変動やエネルギー政策などに関してはど素人であることをはじめに申し上げておきます。
そんな僕が研究費申請などで、「錦の御旗」として気候変動問題の(間接的な)解決を謳っていることに少しの負い目を感じていた。というのが、最近気候変動やエネルギー政策に関する書物を「趣味」として読むようになったきっかけです。
以前YouTubeで「天然ガスと液化天然ガスって同じじゃない?と思っている人が観る動画」と題して、天然ガスと液化天然ガス(LNG)の違いを説明する動画を配信し、言論プラットフォームアゴラでもその動画記事を紹介していただきました。
その動画を観てくださった岩瀬昇さんがツイートで
ガスの技術性状から生ガス(業界用語)とLNGの違いを解説している初心者向けとしては意義のある動画。だが「パイプラインガスは安い、LNGは高い」は大きな誤解ですので、ご注意を。他にもいくつか根本的誤解がありますが、略。長い間ガスは中途半端なエネルギーとみなされており、石油を求めて掘削 ZXci9ikf
— nobbypapa (@nobbypapa1948) September 23, 2022
とコメントをくださったのが、岩瀬さんを知るきっかけです。
「「パイプラインガスは安い、LNGは高い」は大きな誤解」「他にもいくつか根本的誤解があります」とご指摘くださり、岩瀬さんの著作「石油の「埋蔵量」は誰が決めるのか」をご紹介してくださったのを受けて、その書評も動画記事にすることができました。専門家の方から直接、しかも無料でご指導いただける経験は、インターネット時代の醍醐味だと感じました。そして、僕のエネルギーに纏わる理解が飛躍的に伸びたという経緯があります。
「石油の「埋蔵量」は誰が決めるのか?エネルギー情報学入門」
前置きが長くなってしまいましたが、今回紹介する本は、石油や天然ガスを専門にされているエネルギーアナリストの岩瀬昇さんのエネルギー、特に石油と天然ガスをめぐる世界の、そして日本の政情を理解し、今後を予測するための新刊本です。
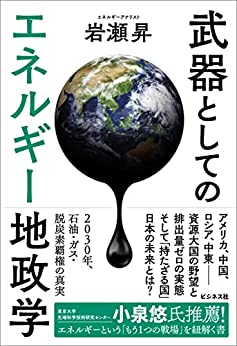
岩瀬昇(著)「武器としてのエネルギー地政学」
本書は、全7章で構成されています。
冒頭の第一章の、ロシアのウクライナ侵攻に関するエネルギー問題から見た考察は圧巻です。本の帯で本書を推薦されている、ロシアの専門家、小泉悠さんとの会話や、ロシア人の気質などのやりとりを読んで、石油と天然ガスの科学技術的なことの基本的な理解だけではなく、国家間の文化や政治が複雑に絡むエネルギー問題の奥深さに、思わず唸ってしまいました。
それに続く第二章は、気候変動問題で世界をリードする(?)ヨーロッパの「環境先進国」としての苦悩、そして第一章のロシアのウクライナ侵攻の原因を示唆するエネルギーのロシアへの依存にスポットライトを当てて、エネルギー安全保障の本質を炙り出しています。
第三章は、実は世界最大の産油国であるアメリカに話題は移り、「シェール革命」の背景を詳しく、そして「石油の埋蔵量」に関するトリックの種明かしをされています。断片的なニュースで耳にする「シェールガス」「シェールオイル」そして「石油の埋蔵量」に関する知識を系統的に、しかも面白く学べました。
アメリカの次は当然中国。というわけで第四章は「エネルギー百年の計」を着実に、そしてしたたかに進める中国のエネルギー事情に関してです。中国はスケールの大きさだけではなく、時間軸の長さに関してもスケールが大きく、日本は多くのことを中国から学べるのではないかと感じました。本書にはあまり登場しませんが、西側諸国との社会システムの違いから、原子力発電は今やロシアと中国の独壇場となっています。










































