核革命論
全ての核政治論の土台は、Robert Jervis, The Meaning of Nuclear Revolution, Cornell University Press, 1989の核革命理論です。
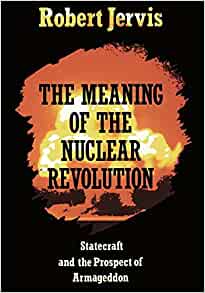
ここでロバート・ジャーヴィス氏は、戦略家のバーナード・ブローディ氏の「核兵器は軍隊の役割を戦争に勝つことから、戦争を防ぐことに変えた」という主張を発展させました。すなわち、核兵器は国家に究極的な安全保障を提供する(核武装国の生存を脅かす戦争行為は危険すぎてできなくなった)だけでなく、核保有国間では戦争や危機でさえも起こりにくくなり、敵国に耐え難い損害を確実に与えられる核報復力(第二撃能力)を超えた核戦力は政治的に無意味であることを強力な理論として提示しました。
■
スコット・セーガン、ケネス・ウォルツ、齋藤剛訳『核兵器の拡散』勁草書房、2017年(原著2013年)。

日本語で読める数少ない核政治の書籍です。ここでケネス・ウォルツ氏は、国家が抑止されるのは、核攻撃から受けるコストが利得を上回ると認識するからではなく、核戦争の恐怖であると力説しています。
抑止は、コスト>利得という合理性の観点からよく議論されますが、彼は、こうした「合理性」の議論を否定しています。くわえて、ウォルツ氏は核抑止が戦争を防ぐので、核保有国が増えるほど世界は平和になるだろうと考えています。
他方、スコット・セーガン氏は、組織論が教えるところは、偶発的核戦争などのリスクを無視できないことであり、核兵器を保有する国家が増えると、世界は危険になると反論しています。
■
Keir A. Lieber and Daryl G. Press, The Myth of the Nuclear Revolution: Power Politics in the Atomic Age, Cornell University Press, 2020.
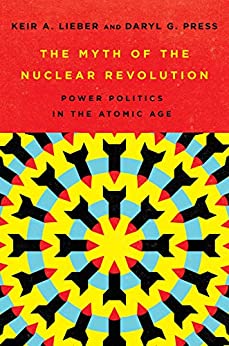
ケイル・リーバ氏とダリル・プレス氏による核革命論への反論です。彼らによれば、国家は第二撃能力を持っても、より確実な安全保障を求めて競争を続けることになります。
■










































