一般の建築、とくに公共施設についても、軍事攻撃に強いようにし、防空壕・核シェルターとしての機能をある程度持たせるように建築基準の改正をすべきだろう。昭和初期の公共建築はそうした配慮がされていて、財務省庁舎など天井が分厚いので、携帯電話初期にはつながらなかったほどだ。
こういう費用は、防衛費に勘定しても構わない。武器を買うばかりが防衛費ではない。
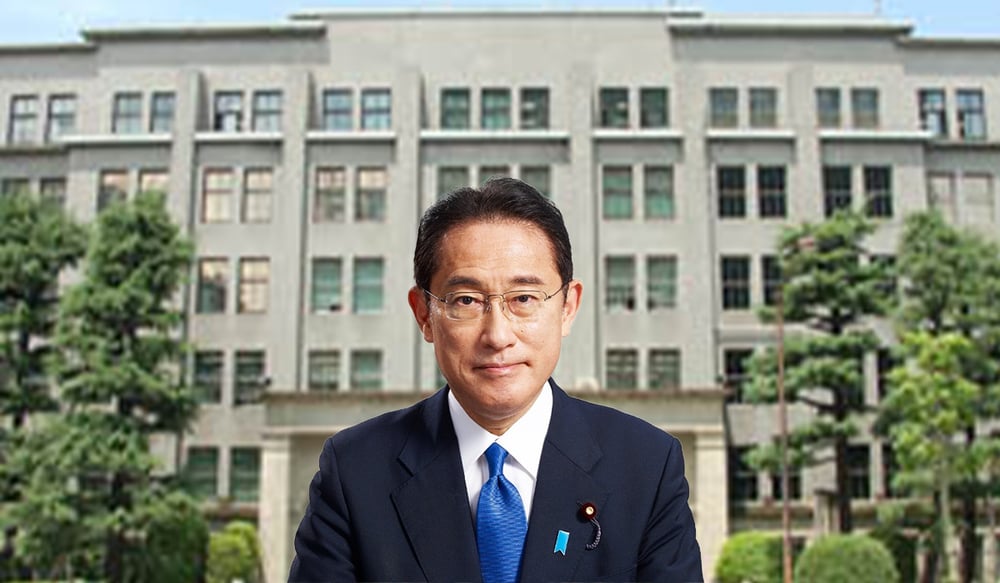
岸田首相 自民党HPより / 財務省庁舎 同省HPより
科学技術研究も防衛力強化に役立つものに傾斜すべきだし、それは、防衛費からどんどん支出すればいいし、ある程度は、既存の研究費を削ればいい。学術会議が協力しなければ、廃止などを迫ればいいことだ。
PKOも含めた海外派兵についても、ある程度は拡大すべきだ。日本がそれを回避しているのは、憲法問題もさることながら、戦死者ゼロに拘りすぎだ。たとえば、消防士が燃える建物には入らないと決めたら、殉職者は減る。しかし、焼死者はかなり増える。
自衛隊も訓練では殉職者をある程度、出している。海外で全体の殉職率をさほど上げない程度の運の悪い殉職者を出すのが何より避けるべき目標ではあるまい。それに、現在の自衛隊の殉職率は、トラックの運転手の10分の1くらいである。
ちなみに、自衛隊員や海上保安庁などだけで無く、日本の外交官や交際協力関係の職員も現在よりは、危険な土地に生命の危険があっても留まるべきだ。詳しい経緯は不明だが、アフガニスタンから逃げ出すのとか、キーウについてもあまりにも自分たちの安全重視が極端過ぎる。
大企業ではない民間の現場の人たちの人たちとのバランスにおいても、公務員などの安全重視は行きすぎだと思う。
日本は憲法と云うより、戦死者ゼロ神話にこだわるから、過度に臆病で、米軍に頼ったりするから、アメリカから別のところで気前よく金を出すことを要求される。軍事的貢献を改善したら気前の良すぎて日本への見返りが少ないODAなど減らすことができる。
日本はいろんな問題を、気前の良さで補ってきたが、もはや日本は金持ちでない。
また、徴兵は憲法で禁じられるとしても、いまの現状では義勇兵も出てこないし、兵站などで自衛隊や米軍などに民間人が協力するのも難しい。
そこで、私は最近のヨーロッパで検討されている、数週間の公共サービス訓練を国民に男女を問わず義務づけるというのを提案している。そのエッセンスは、アゴラでもまた書きたいが、詳しくは『日本の政治「解体新書」: 世襲・反日・宗教・利権、与野党のアキレス腱』(小学館新書)に書いている。
■










































