目次
カブトムシの標本作りの注意点
カブトムシの標本作りに挑戦!
カブトムシの標本作りの注意点

まず最初に、カブトムシの標本の作り方の注意点です。ご家庭で標本を作る場合の作り方では、薬などを使った防腐処理はしません。また、本格的な標本作成のように、カブトムシの内臓を出して処理するなどの難しい工程もありません。
基本的にご家庭での標本の作り方は、カブトムシを自然に乾燥させて行います。どうしても臭いや虫などが気になる方は標本キットなどを使用していくほうがいいかもしれません。
臭いは大丈夫?

カブトムシやクワガタが死んでまもなくすると、昆虫の内臓の腐敗が進んでいきます。そのため、どうしても腐敗が進むにつれて少々臭いがしてくることもあるでしょう。しかし、これも乾燥が進めばだんだんなくなってくるので、気にしなくても大丈夫。
きちんとした手順で、しっかりカブトムシやクワガタの乾燥ができていれば、カブトムシの標本を作って行く上で臭いの問題ありません。また、標本として保存する頃には臭いもしなくなってきますので、安心して標本作成の作業を進めていきましょう。
昆虫針の種類を知っておこう
昆虫針には有頭針と無頭針があります。標本として針が見えないように見栄えよくしたい方は、昆虫針の無頭針を買いましょう。有頭針は持ち手がついているものです。小さなお子様などと一緒に標本作成をする方には、針を刺す時の安全を考えて有頭針をおすすめします。
昆虫針にはサイズがあります。カブトムシには4~5号、クワガタには3~4号が適しているそう。いずれも昆虫の個体のサイズに合わせて針を選ぶとよいでしょう。数字が上がると太さが太くなります。
カブトムシの標本作りに挑戦!

材料の準備が済んだら、さっそくカブトムシの標本作成に取り掛かりましょう。標本を作るにあたって少々細かい作業や、針を使った作業もあります。小さいお子様などは十分に注意するとともに、安全に行うためにも、保護者の方と一緒に進めるようにしてください。
ステップ1.カブトムシの体を洗う

残念ながら死んでしまったカブトムシに気づいたら、使い古した歯ブラシや小さい筆でカブトムシの体を水洗いしましょう。この時、カブトムシの汚れをしっかり落としていきます。
死んでしまってからすぐ気づいた場合は、カブトムシの足が柔らかい状態ですが、死んでしまってからしばらく経つと足の部分が硬くなってくることがあります。そうなると洗っているうちに足が取れてしまうこともあるので、気をつけながら、やさしくカブトムシの体の汚れを落としながら洗ってあげましょう。
カブトムシの体が硬くなっていたら

カブトムシが死んでしまってから期間が経ってしまうと、足が閉じて硬くなっている場合があります。そんな時は、50〜60度のお湯につけて柔らかくします。
この時、カブトムシをビニール袋などに入れて一緒にお湯を入れて浸しておきましょう。お湯に入れて1〜2時間ほどで硬くなった足が柔らかくなります。中のお湯が汚れで少し茶色になっていれば、カブトムシの体が柔らかくなったことを示しています。カブトムシを取り出して、ティッシュなどで優しく拭いてきれいにします。
足が取れてしまった時は

カブトムシの体を洗ったりきれいにしている間に足が取れてしまうこともあります。そんな時は、カブトムシの体の水分をよく拭いてから、木工用ボンドでくっつけてください。
足が取れてしまった場合は、足の角度などを調整できることから、ステップ2で紹介する発泡スチロールに固定するときに一緒に行うほうがよいでしょう。
ステップ2.カブトムシの標本ポーズを決める

カブトムシの体がきれいになったら、標本作成の準備は完了です。さっそく、標本の作り方に入っていきます。
準備した発泡スチロールに上にカブトムシを置いて、標本にしたいポーズを決めていきます。ポーズが決まったら昆虫針(またはまち針)でカブトムシの足を固定してください。カブトムシの足は、なるべく大きく広げておきましょう。その方がよりリアリティのあるきれいな標本になります。
好きなポーズで標本を作るかたは自分の思いのままに、カブトムシのポーズを決めていきましょう。
固定する際の注意

カブトムシの標本のポーズが決まったら、昆虫針でポーズの固定をしていきます。足を大きく広げてあげて、カブトムシの体に対して90度くらいに足の角度を広げると、美しい標本のポーズになります。もちろん、自分の好きなカブトムシのポーズや動きを見せたい方はこのポーズでなくても構いません。
固定のコツ

カブトムシの足を昆虫針(まち針)で固定する際、足が取れないように気をつけながら、足の爪を発泡スチロールに引っ掛けるようにしてやるとうまくいきます。あとは、足が動かないように昆虫針をそれぞれさして固定していきましょう。
もし足がとれてしまっても、ここで木工用ボンドとピンセットなどで修復していけば問題ありません。ゆっくり慎重に進めていきましょう。
ステップ3.カブトムシの乾燥

カブトムシを固定させたら、このまま乾燥期間に入ります。カブトムシの標本作りの乾燥期間は1~2ヶ月くらいが目安です。乾燥させる際には、直射日光を当てないようにして風通しのよい場所で行いましょう。
乾燥の際に注意したいのが、コバエなどの虫が乾燥中のカブトムシに寄ってきてしまうところ。準備するものにあった、「防虫剤」をそばに置いておいておくことで防げるので、忘れずに防虫剤を置いておきましょう。置き忘れると虫が湧いてしまって大変なことになることもあります。
ステップ4.標本の針刺し

カブトムシの乾燥が終わったら標本づくりも終盤です。乾燥期間がおわったら、カブトムシを標本箱へ移します。固定していた昆虫針をそっと抜きましょう。
標本箱に移し終わったら、カブトムシの体を針を刺していきます。まず、カブトムシの右胸に刺します。この時、垂直に刺して行くのがポイント。斜めに刺したり胸の真ん中に刺してしまうと羽が歪んで開いたりしてきれいな標本になりません。せっかくの長い乾燥期間がここで台無しになってしまわないよう慎重に針刺しを行いましょう。
足の針刺し

胸の針をカブトムシの体に貫通させたら、標本箱にそのまま刺していきます。あとは、足を針で固定していくだけ。足の針は、関節や爪の部分に引っ掛けるようにして固定すれば大丈夫です。
標本箱を動かした時に、カブトムシの体がずれないようしっかり固定してきましょう。全部の足に一本づつ針刺しをしたら、いよいよ完成です。
ステップ5.最後の仕上げ
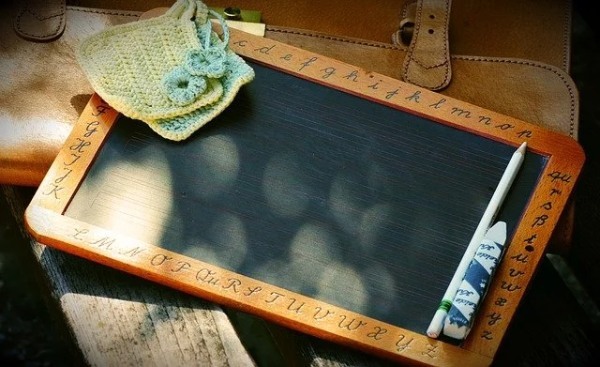
最後に必ず、防虫剤を一緒に入れておいてください。入れ忘れてしまうと、虫が発生して大事なカブトムシの標本どころが標本箱の中が大変なことになってしまいます。せっかく長い期間かけて完成したカブトムシの標本を台無しにしないよう、保存の際には防虫剤だけは忘れないようにしてください。
大切に育てたカブトムシ。標本を作成して、カブトムシの思い出をかっこよく残せるのなら、お子様もきっと大満足すること間違いでしょう。
標本をより本格的にしてみよう

ここで、作った標本をよりかっこよく本格的なものにするためのコツを教えましょう。それは標本箱にラベルを貼り付けることです。
ラベルには、カブトムシを採った場所や日付、名前などを書いておくとより本格的な標本に近づきます。お子様の名前を書くだけでも、とても喜んでもらえるかもしれません。数種類の甲虫類の標本を作って標本箱にまとめれば、より本格的な標本作成になります。色々な甲虫類の標本を作ってみても楽しいでしょう。
6.カブトムシの標本完成!

標本箱にしっかりカブトムシを固定し、防虫剤を入れ、蓋をしたら完成です。一生懸命お世話したカブトムシの標本は、きっととてもよい思い出として残ることでしょう。
カブトムシだけでなくクワガタなどの甲虫類であれば、同じ方法で標本を作ることが可能です。標本作成や標本箱作りは、夏休みの工作などにも最適。高学年ならひとりでも作成できるくらい簡単な工程で標本作成はできるので、ぜひ一度挑戦してみてはいかがでしょうか。











































