遺産分割協議は相続人同士で遺産の分け方を話し合うプロセスです。決まったやり方はありませんが、「全員の合意が必要」というルールがあります。協議の進め方や、話し合いがまとまらない場合の解決方法を解説します。
遺産分割協議とは?
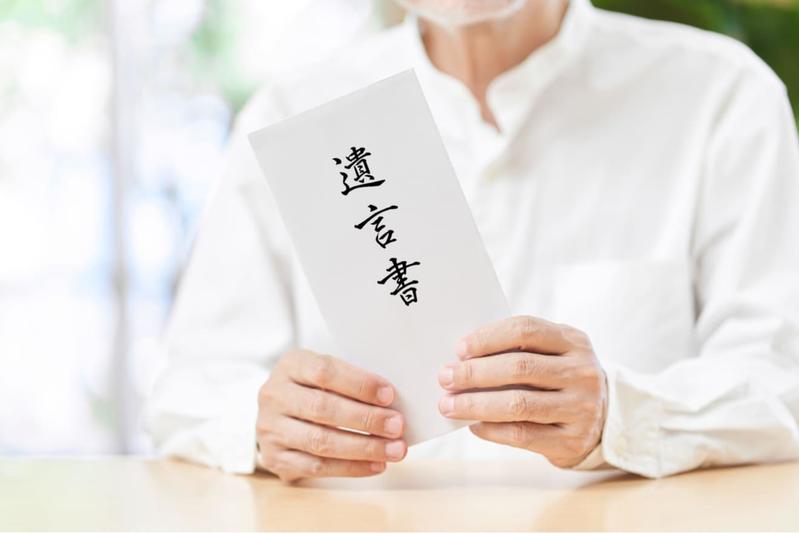
故人(被相続人)が遺言書を作成していない場合や、遺言内容と異なる遺産分割を行う場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議にはどのような方法があり、いつまでに行えばよいのでしょうか?
相続人で遺産の分け方を話し合うこと
遺産分割協議とは、故人の財産について「誰が・何を・どのくらい引き継ぐか」を相続人全員で話し合うことです。民法907条には、以下のような記載があります。
第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
引用:民法907条 | e-Gov法令検索
遺言書がない場合、財産を相続できる相続人は民法によってあらかじめ決まっています(法定相続人)。法定相続人以外が財産を引き継ぐのは、遺言書によって遺贈を行う場合のみと考えましょう。
複数の人が相続人になった場合、全員で遺産分割協議を行い、誰がどのように財産を取得するかを決定します。協議内容は「相続人全員の合意」がなければ成立しません。
1カ所に集まって話し合うのがベストですが、集まるのが困難な場合は、電話やメールなどで承諾を得ることも可能です。
参考:民法907条 | e-Gov法令検索
期限はないが早めがベター
遺産分割協議に期限はありませんが、できるだけ早めに行うのが理想です。相続税の申告期限までには済ませるようにしましょう。
相続税の申告・納付期限は「亡くなったことを知った日の翌日から10カ月」です。この日までに遺産の分け方が確定していない場合、財産を法定相続分(民法が定める相続割合)で相続したと仮定して相続税を納める必要があります。
未分割の財産には「配偶者控除の軽減」や「小規模宅地の特例」といった減税措置が適用されません。先に法定相続分で申告・納税をし、遺産分割協議後に「更正の請求」をすれば納め過ぎた税金の還付が受けられますが、手続きに手間がかかります。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は、以下のような手順で進めるとスムーズです。
- 相続人の確定
- 相続財産の調査・財産目録の作成
- 相続人全員による遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は相続人が一人でも欠けると無効になるため、相続人の確定は最も重要なプロセスといえます。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せて、徹底的に調査しましょう。被相続人が離婚・再婚している場合、元配偶者との間に生まれた子も法定相続人です。
相続財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や債務などのマイナスの財産も対象です。相続財産の調査後は財産目録を作成しましょう。
相続人全員で遺産分割協議を行い、内容に合意が得られたら「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割で合意に至った内容を書面に記したものです。作成者は「相続人全員」で、相続人全員が自署・押印を行います。遺産分割協議書が必要になるシーンや、作成のポイントを確認しましょう。
遺産分割協議書は必要か?
遺産分割協議書は「遺産相続に関する各種手続き」で必要とされるものです。ただし、以下のようなケースにおいては、遺産分割協議書の提出を求められることはないでしょう。
- 相続人が1人しかいない場合
- 遺言書の通りに遺産分割を行う場合
- 法定相続分通りに遺産分割する場合
- 名義変更が必要な財産(不動産・有価証券など)がなく、相続税の申告も不要な場合
遺産分割協議書には、相続に関するトラブルを未然に防止する役目もあります。口約束だけでは「言った言わない」で、あとからもめる可能性があるでしょう。相続人が複数いる場合は手続きに必要がなくても、遺産分割協議書を作成しておくのが賢明です。
遺産分割協議書の提出先
遺産分割協議書は、以下のような手続きにおいて提出を求められるケースがあります。いつまでに作成しなければならないという決まりはありませんが、手続きを滞りなく進めるためにも、できるだけ早く作成するのが望ましいでしょう。
- 相続税の申告手続き:被相続人の住所地を所轄する税務署
- 相続登記手続き(不動産の名義の書き換え):不動産の所在地を管轄する法務局
- 車の名義変更手続き:車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
- 株式の名義変更手続き:証券会社
- 預金の払戻手続き:金融機関
前述の通り、遺言書や法定相続分に応じて分割する場合は、遺産分割協議書は必要ありません。
必要事項と書き方のポイント
遺産分割協議書には決まった書き方はなく、手書きでもPCで作成しても構いません。必要事項がきちんと盛り込まれており、かつ相続人全員の自署・押印があることが最も重要なポイントです。以下は記載事項の一例です。
- 被相続人の情報(氏名・生年月日・死亡日・本籍地・最後の住所)
- 相続人全員が遺産分割の内容に合意している文言
- 各相続人が取得する相続財産の詳細
- 未分割の相続財産が見つかった場合の対応
- 相続人全員の氏名と住所
財産が預金の場合、金融機関名・支店名・預金口座の種類・口座番号まで記載します。
不動産については、「不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)」と相違がないように記載しましょう。内容に相違や不備があると、遺産分割協議書を改めて作り直さなければならなくなるケースもあるようです。
相続人の自署と押印が必須
遺産分割協議書の内容に同意したことを示すために、相続人全員の自署と押印が必要です。押印は「実印」が原則で、「印鑑証明書」も添付します。
相続人全員が1カ所に集まれない場合は、電話やメールで内容を話し合ったうえで、代表者が遺産分割協議書を作成します。親族A→親族B→親族Cといったように、1通の遺産分割協議書を順番に郵送し、それぞれに自署・押印をしてもらいましょう。
相続人の数が多い場合、相続人ごとに遺産分割協議書を作って郵送し、それぞれに自署・押印をしてもらう方法もあります。この書面は「遺産分割協議証明書」とよばれ、すべての枚数がそろうと遺産分割協議書と同等の法的効力を有します。









































