入社前の仕事とのギャップに不満があったり、他にやりたいことが見つかったりした場合、転職を検討することがあります。しかし、今の会社を辞めなければ、次のステップに進むことはできません。今すぐにでも会社を辞めて、新しい職場を探したいと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。当記事内では円満に退職するために押えておくべき大切なポイントをご紹介しますので、ぜひお役立てください。
目次
会社の辞め方(退職)の手順
会社を退職する理由の伝え方
会社の辞め方(退職)の手順
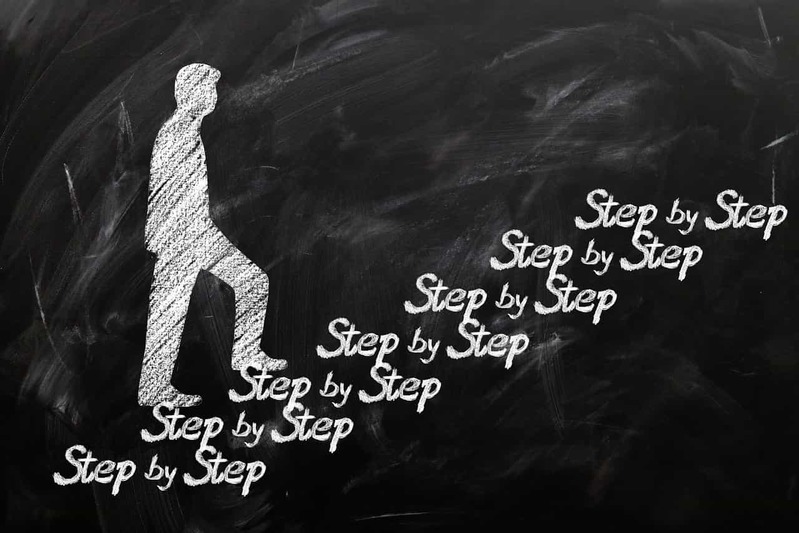
会社を辞める決心がついたら、まずは退職日までにやるべきことを把握することから始めましょう。退職までの流れを大まかに把握しておくだけで、計画を立てやすくなります。ここでは、退職から入社までの流れについて解説します。
会社の辞め方①プランを立てる
退職が決まったら、退職の計画を立てましょう。法律により、退職の意思は退職日の2週間前までに伝える必要があります。会社の就業規則によっては、1~2ヶ月前に退職の意思を伝える必要がある場合もありますので、注意が必要です。
ただし、原則的には退職の意思表示をしてから2週間後であれば、退職することができます。残っている有給休暇の日数の確認も忘れずに行いましょう。
会社の辞め方②上司に退職を申し出る

退職願は直属の上司の了解を得た上で提出するのがマナーです。後任者を決め、引継ぎスケジュールを組む必要があるため、退職の意思表示を受けた上司は、部長や役員と話し合いをしなければなりません。
このようなプロセスを経て、退職が正式に決定されますので、退職願は会社が退職に同意した後に提出するようにしましょう。
退職願の提出期間は会社の就業規則で定められていますが、引き継ぎ期間を最大限に活用できれば、会社の負担も少なくなります。円満退職を実現するためにも、業務終了や引継ぎ期間を考慮した退職スケジュールを立てるようにしましょう。
会社の辞め方③退職届を用意し提出
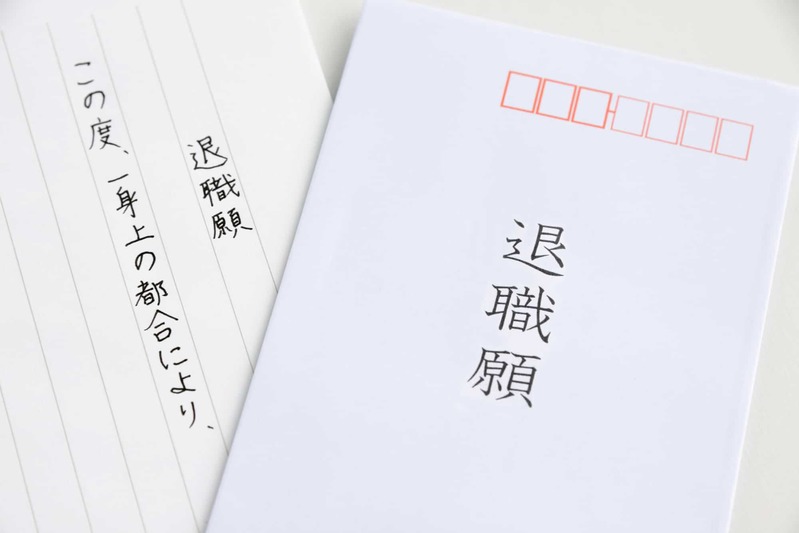
退職願・退職届はどんな場合でも提出する必要があるのでしょうか。自己都合、会社都合、契約期間満了の場合に分けてみてみましょう。
まず、自己都合の場合は、退職願・退職届を提出する必要があります。退職願は一方的な退職の意思表示ですので、退職願を提出する方が一般的です。
会社都合で退職する場合は、退職願や退職届を提出する必要はありません。退職届を提出すると自己都合扱いになり、失業保険の手続きで給付日数の減少や給付制限など不利な扱いを受ける可能性があります。

会社都合であるにも関わらず、退職願や退職届の提出を求められた場合は、必ず退職理由を明確に記載しましょう。例えば、退職を勧められた場合は、「退職を勧められたため退職します」と明確に記載します。
契約期間満了の場合は、退職願や退職届を提出する必要はありません。ただし、契約更新を希望していた場合とそうでない場合では、失業保険の条件が異なります。
契約更新を希望していた場合は、退職届に「契約更新を希望していましたが、契約期間満了に伴い退職します」など退職理由を明記し、退職の証拠を残しておくことが大切です。
会社の辞め方④引継ぎをする

引き継ぎは義務ではないとはいえ、円満退職のためには欠かせないものです。きちんと行わないと、他の社員の業務が滞ったり、最悪の場合、会社に損害が発生することもあります。
引き継ぎをしなかったことで損害賠償を請求されるケースもありますが、引き継ぎをしなかったことで損失が生じたことを証明するのは難しいため、賠償金を支払う必要がない場合がほとんどです。

とはいえ、引き継ぎを行うことは社会人としてのマナーです。きちんと行い、笑顔で退職の日を迎えましょう。引継ぎの時期は、退職の1~3カ月前くらいが多いようです。
これは、就業規則に「退職希望日の1~3カ月前までに上司に退職の意思を伝えること」と定めている会社が多いからです。勤務体系にもよりますが、多くの場合、退職日が決まった時点で引継ぎが始まります。
会社の辞め方⑤退職日を迎える

引継ぎが終わったら、会社に機器を返却し、退職日を迎えましょう。退職時に受け取る主な書類と返却する備品は次のとおりです。
【会社に返却する備品の例】
- 身分証明書
- 名刺
- 健康保険証
- 書類、パソコン、データなど
【退職後に受領する書類例】
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
どんな書類が必要で、どんな書類が届くのかがわかれば、よりスムーズに退職・転職することができます。ただし、企業によって異なる場合がありますので、必ずご自身でご確認ください。
会社を退職する理由の伝え方

退職する際には退職理由を伝える必要がありますが、「誰にどのように伝えればいいのか」と悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、退職理由の伝え方のコツをご紹介します。
伝え方①まずは直属の上司から

直属の上司に退職の意思を伝えるのは、自分の意志が固まってからにするのがマナーです。上司に退職の意思を伝える前に、あなたの意思に関する噂や事実でないことが広まらないように十分に注意する必要があります。
人によっては、同僚や部下に内緒で退職の意思を伝えたいと思うかもしれません。そのような場合でも、直属の上司に伝えるまでは、噂が広まらないように注意する必要があります。
直属の上司に言いづらい、話したくないという場合でも、他部署の上司に話すのは社会人としてふさわしくありません。まずは直属の上司に伝えるのがマナーです。
直属の上司に伝えた後、退職を認めてもらえないなど、理不尽なことがあった場合は、上司や人事部に伝えても問題ないでしょう。
伝え方②退職時期を明確にしておく

辞めたくても、会社に引き止められるから辞められないというケースは少なくありません。会社にとって戦力となる社員であれば、退職を思いとどまるように圧力を受ける可能性が高くなります。
また、業務を引き継ぐスタッフが不足している場合は、後任が見つかるまで待ってくれと言われることもありますし、重要なプロジェクトの途中であれば、「このプロジェクトが終わってから改めて話そう」と、退職の延期を求められることもあります。
そうなると結局退職のタイミングを逃してしまうかもしれません。そのため、退職を伝える際には、退職日を明確に伝えることが大切です。民法627条によると、雇用期間の定めのない契約の場合、労働者が退職の意思表示をした後、原則として2週間以内に退職することができます。
伝え方③電話

基本的には、電話のみでの退職連絡は認められません。ただし、やむを得ない事情がある場合は、認められることもあります。
例えば、長期入院が必要な怪我をした場合や、完治の見通しが立たない精神疾患を患っている場合などは出社が困難なため、事情を説明すれば、電話で受け付けてくれるかもしれません。
また、職場でパワハラやセクハラの被害に遭った場合、電話による退職の連絡はやむを得ないでしょう。他のケースでは、突然家族が倒れてしまい、急遽、家族の介護のために実家に引っ越しせざるを得なくなるケースもあります。
介護度にもよりますが、重度であれば介護対象者から離れることはできないので、電話で退職の旨を伝えることが許される場合もあります。また、電話をかけることすら怖いという方は、退職代行サービスを利用するのも一つの手かもしれません。
電話で退職を伝えるときの注意点

曖昧な言い方をすると、退職の意思が伝わらず無断欠勤扱いになる可能性もありますので、はっきりと意思を伝えるようにしましょう。
また、人によっては電話で退職の意思を伝えられることに違和感を覚えるかもしれません。そのため、直接伝えることができない事情を説明し、謝罪の言葉を添えましょう。お詫びの気持ちを伝えるだけで、相手に好印象を与えることができます。









































