目次
ケースワーカーに必要な資格
ケースワーカーに向いてる人の特徴
ケースワーカーに必要な資格
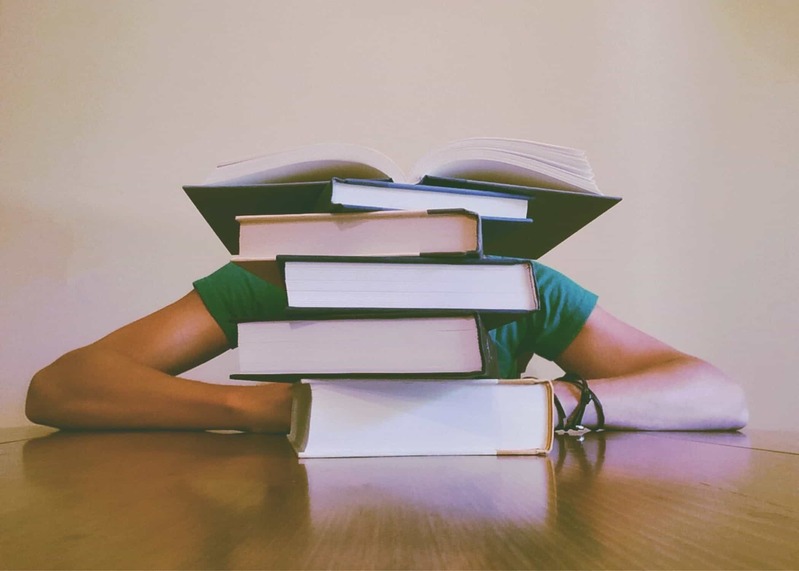
ケースワーカーになりたいと思っている方は、必要とされる資格取得のプロセスにも興味があるのではないでしょうか。ここでは、ケースワーカーに求められる資格について取り上げます。
資格①社会福祉主事

福祉事務所で働くケースワーカーになるためには、まず社会福祉主事任用資格を取得する必要があります。社会福祉主事任用資格は、大学や短大で社会福祉に関する科目を履修するか、厚生労働大臣が指定する養成機関や講座を修了することで取得できます。
また、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持っていれば、社会福祉主事として働くことができます。各自治体が実施する地方公務員試験に合格し、社会福祉主事として配属されて初めて、ケースワーカーとして採用されます。
したがって、公務員試験に合格したからといって、必ずしもケースワーカーとして働くことができるわけではありません。また、自治体によっては、社会福祉関係の採用枠があるところと、一般行政職の採用枠があるところがあります。
資格②児童福祉司

児童福祉司になるためには、児童福祉司としての任用資格が必要になります。この資格を取得するには、心理学、教育学、社会学を専攻した大学を卒業するか、厚生労働省が指定する福祉施設で1年以上の実務経験を積むか、都道府県知事が指定する養成機関を卒業するなどの方法があります。
また、医師や社会福祉士などの有資格者も児童福祉司に任命されることができます。しかし、実際に公務員にならないと任用資格が適用されないため、任用資格を得て地方公務員試験に合格し、児童相談所に配属されて初めて児童福祉司を名乗ることができます。
資格③社会福祉士や精神保健福祉士

社会福祉士も精神保健福祉士も相談援助専門職であり、職名を名乗るためには登録が必要な名称独占資格です。人々のニーズや時代の変化に合わせて、支援の範囲も広がっています。
社会福祉士と精神保健福祉士の仕事と役割ですが、まず、社会福祉士は、身体や精神に障がいのある方だけでなく、低所得や家庭環境などの環境的な理由で日常生活に支障をきたしている方への支援を行います。
精神保健福祉士は、主に精神疾患の治療を受けている人や精神障害を持つ人を対象に、社会復帰や日常生活への適応を支援します。
ケースワーカーに向いてる人の特徴

人の悩みや問題に日々応対するケースワーカーには、さまざまな能力が求められます。ここでは、どんなタイプの人がケースワーカーに向いているのか、3つの特徴をご紹介します。
特徴①人の話に耳を傾けられる

不安を抱える人の内面を深く理解するためには、じっくりと話を聞き、要点を押さえた質問ができるコミュニケーション能力が必要です。相談者はそれぞれ、置かれている状況も、考え方も、抱えている問題も異なります。相手の立場に立って考え、的確なアドバイスができる人がケースワーカーに向いていると言えます。
特徴②人の役に立ちたい

大切なのは、社会福祉に関心と熱意を持ち、問題や障害を抱えている人を助けたいという奉仕の精神を持つことです。また、信頼感、包容力、優しさなども求められます。
また、現状を把握し、最適な解決策を見出すためには、相手の話をよく聞き、感情に左右されずに冷静に判断する力が必要です。また、すぐには解決できない問題も多いため、粘り強く物事に取り組む姿勢も大切です。
特徴③臨機応変に対応できる

ケースワーカーとして働いていると、自分だけではどうにもならない難しい問題に直面することが多々あります。どうやっても解決策が見つからない、問題や相談を受けたとしても、臨機応変な対応が求められるのです。
ケースワーカーが感情的になりすぎると、相談者との関係が崩れ、信頼関係を築くことができなくなってしまう可能性があります。そのため、ケースワーカーには、現状の課題を正しく把握し、冷静に判断し、柔軟に問題を解決していくなど、常に第三者としての視点が求められます。









































