わたしは戦争終結について、以前から、ある1つの疑問を抱いていました。それは第二次世界大戦の初期において、なぜイギリスはドイツと和平を結ばなかったのか、というパズルです。
周知の通り、1940年5月に発足したチャーチル戦時内閣は、フランスが降伏寸前まで追い詰められ、アメリカは「孤立主義」を保っており、ソ連はドイツとの不可侵条約により参戦が望めない、孤立した絶望的な状況に追い込まれていました。それにもかかわらず、イギリスは圧倒的な優勢を誇っていたナチス・ドイツの和平の呼びかけに応じず、徹底抗戦を決断しました。どうしてなのでしょう。

gionnixxx/iStock
民主主義のために抵抗したイギリス?
この点について、千々和泰明氏(防衛研究所)は『戦争はいかに終結したのか』(中央公論新社、2021年)で示した理論による説明を試みています。かれは戦争終結の因果関係をいくつかの主要な仮説にまとめています。
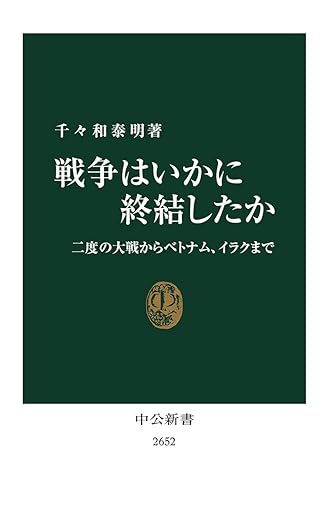
第1の仮説は、「優勢勢力側にとって『将来の危険』が大きく『現在の犠牲』が小さい場合、戦争終結の形態は『紛争原因の根本的解決』の極に傾く」です。第二次世界大戦の終わり方は、これを裏づけるものです。
第2の仮説は、「優勢勢力側にとっての『将来の危険』が小さく『現在の犠牲』が大きい場合、戦争終結の形態は『妥協的和平』の極に傾く」です。湾岸戦争の帰結は、このパターンに当てはまります。(同書、18-19ページ)。
千々和氏によれば、イギリスのドイツに対する徹底抗戦は、第1の仮説にそっているということのようです。
「ドイツと海峡を隔てるイギリスには、勝算がまったくないわけではなかった。何よりもイギリスは、まだアメリカ参戦の可能性があると信じることができた。イギリスは、自国を守ろうとしている民主主義という価値が『現在の犠牲』に耐えるのに見合うものだと考え、また構造的なパワー・バランスを自国に有利なかたちで変えうる可能性が客観的に存在すると判断することができた…劣勢勢力側が考えなければならないのが、自らの損害受忍度についてである。チャーチルのイギリスは民主主義のため…『現在の犠牲』に耐え、成功した」。










































