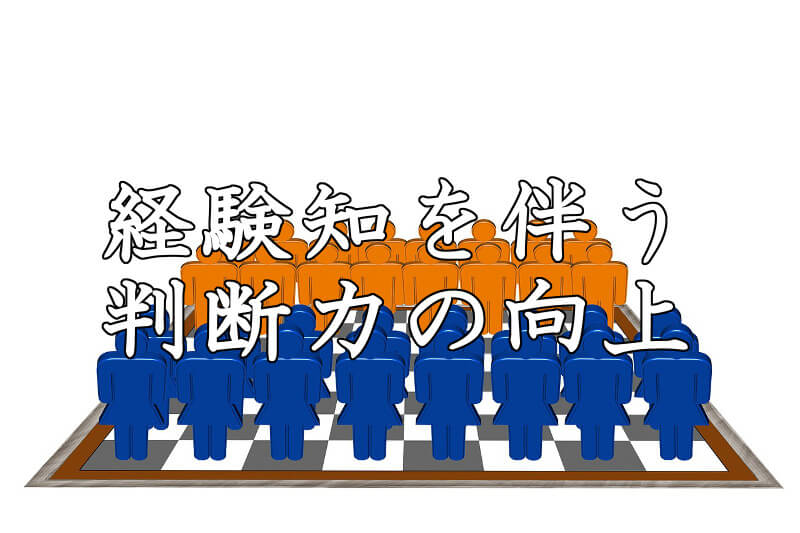
日本経済新聞に本年2月末日、「かつての自分とは競わない 58歳に寄せて(三浦知良)」という記事が掲載されていました。我々は過去の自分と、如何に向き合うべきでしょうか。
人間、歳と共に身体的能力は確実に落ちて行きます。また、記憶力の一部についても落ちる所はあると思います。しかしそれ自体、当たり前の話で卑下して悲しむ必要性はありません。
人間、歳と共に必ずプラスの部分も出てきて増して行きます。それ即ち、経験知や直観力あるいは判断力といった類です。従って脳の働きということでは、必ずしも過去に比して落ちているわけではありません。
自分にそれなりの社会的地位も出来始め、人に影響力を与え得るステージに立ったらば、年を経て高められた上記能力を発揮すべく適合した環境が、きちんと目の前に用意されていることでしょう。
概して判断の多くは、理詰めでやったつもりでも理詰めになどなっていないものです。本来様々に考慮せねばならない沢山の事柄が抜け落ちているのが殆どですから、基本「エイヤー」の世界であります。
但し経験知を重ねる中で直観力が向上し、より良いパフォーマンスが出せるようなって行くケースが多々あるのも事実です。羽生善治さんの言葉を借りて言えば、之は経験によって羅針盤の精度が段々と上がって行くイメージです。
直観とは、「五感(…目・耳・舌・鼻・皮膚を通して生じる五つの感覚)を通すことなく、思考を働かすことなく、心で直接認識すること」、と私は定義しています。様々な事柄が絡み合った複雑系の現実において、成功確度高くスピーディーな判断を下すべくは、経験知を上げ直観力を養って行くしかありません。
精神的練磨や学問的練磨あるいは経験的練磨といった全てが合わさって、一つの道が出来てくるということだろうと思います。例えば、凡そ二千数百年という長い人類の歴史の篩に掛かった書物は人格を陶冶し続けた先哲達の直観的知恵、徳慧(とくけい、とくえ…終局悟りに至る実践的な智慧)とも言い得るものの結晶であり、我々は古典を学ぶ中でその直観的な知恵を学ぶことが出来ましょう。










































