貿易DXの未来
** ――貿易DXの可能性を実感したのはいつ頃ですか? **
** 佐藤氏 ** :コロナ以前は、まだまだ貿易DXは現実味が薄いと捉えられていました。しかし、パンデミックが全てを変えました。
物流の現場ではそれまで、毎朝出社して顔を合わせ「あの書類はどうなってる?」「船は予定通り入港する?」と口頭で確認しながら業務を進めていましたが、それがいきなりできなくなってしまった。パンデミックの影響で業務のやり方の前提が崩壊し、情報共有の方法を変えなければならないという喫緊の事態に直面し、業界全体の意識が一変したのです。
それを契機に”デジタルフォワーディング”という概念や、クラウドで業務進捗、情報、コミュニケーションを一元管理できるShippioの仕組みに興味を示していただける方が増え、導入企業が拡大していきました。パンデミックは、ある意味で、貿易業界のデジタル化を大きく加速させる契機となったと言えるでしょう。
** ―― そして2022年には老舗通関会社のM&Aも実行しています。この狙いは? **
** 佐藤氏 ** :狙いは通関事業への参入です。当初フォワーダー事業参入と同様に自社で免許(通関業許可)を取得しての参入を考えていました。しかし非常に難易度が高く時間も要しそうでした。そこで通関業許可を持つ企業と一緒になる、”アクライセンス”を狙ったM&Aを考え始めました。
スタートアップが60年の歴史ある老舗企業をM&Aする。当時としてはあり得ない発想だったかもしれません。M&Aは相手がある話です。実際、M&A対象企業の経営陣や社員の方々は「よくわからないスタートアップに、自分の会社の社員や顧客を引き継いでいいものなのか」と、最初は困惑されたと思います。
私たちのような新しい企業が、歴史ある企業の意志や文化を尊重しながらも変革を推進できるか? それを問われる挑戦でもありました。
** ――M&Aを進めるにあたって、対象企業の経営陣やVCなどとの関係構築はどのように進めていきましたか。 **
** 佐藤氏 ** :まずは対象企業に関してです。似たようなテック系企業をM&Aするのであれば、相手も慣れているので話は進めやすいと思いますが、老舗企業の場合「御社がうちを買う? なんで?」というところから話が始まるわけです。まず、ここで信頼を得る必要があります。交渉時には、先方に対して当社のビジョンや技術力、そして社員のキャリアプランまで具体的に提示し、丁寧に説明を重ねました。信頼関係を構築するために何度も足を運び、互いの共通点や未来への展望を語り合いました。
投資家に関しては、シリーズBで調達した資金をM&Aに使うわけですから、投資家に理解をしてもらえるよう話し合いを重ねる必要があります。ましてや、あまり前例のないスタートアップによる老舗のM&Aですから。当初は懐疑的な意見もありましたが、事業計画の緻密さと私たちの強い意志を伝え続けることで、最終的に理解を得ることができました。
商社での自分の経験や、ベンチャーでのM&A、PMI推進経験のある当社役員の存在、そしてこの異例とも言えるM&Aの可能性を信じてくれた方々のご支援もあり、実現にこぎつけました。
** ――貿易事業においては行政とのやり取りも含まれると思います。この辺りについてはいかがですか。 **
** 佐藤氏 ** :行政とのやり取りもM&Aと同様に、こういったスタートアップの前例がなかったため、理解を得るのに最初は苦労しました。しかし粘り強くデジタル化によって得られる効率性や透明性、そして日本の貿易競争力向上への貢献といったメリットを、具体的なユースケースを交えながら説明しました。
2023年からは経済産業省が主導して推進している貿易手続きのデジタル化推進に向けた議論に参加し、連携を深めています。経産省から2024年6月に公表された貿易手続きデジタル化に向けたアクションプランでは「令和10年度までに貿易PFを通じてデジタル化された貿易取引の割合を10%とする」という明確な目標が示されています。貿易DXのプラットフォーマーとして、Shippioもこの目標達成に向けて貢献できればと考えています。
また、2022年にM&Aした老舗通関事業者の協和海運と共同で、DXコンテスト「日本DX大賞2025」(主催:日本DX大賞実行委員会)において、「事業変革部門」の大賞を受賞いたしました。
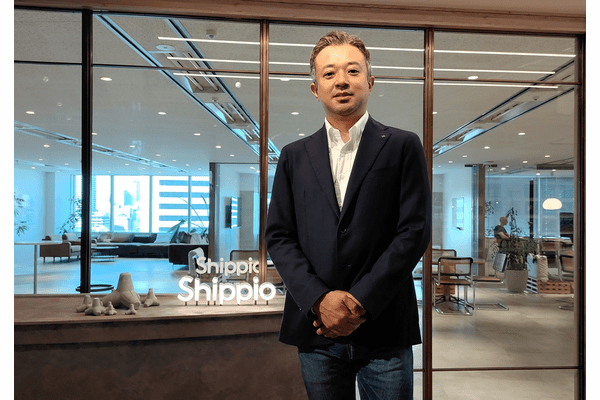
** ――それでは最後に、今後のビジョンをお聞かせください。 **
** 佐藤氏 ** :まずは貿易の総合プラットフォーム「Shippio platform」を構築し、私たちのビジョン「国際物流を、アドバンストに」を実現していくことです。
従来のアナログな国際物流の状況をDXでなめらかに変革することが当社の出発点です。しかし、国際物流は関係者も複雑なプロセスも多いため、一気にすべてをデジタル化することは困難です。そこで、まずは船の遅延状況をリアルタイムで把握できるトラッキングシステムや、関係者間のコミュニケーションを円滑にするツールなど、部分的なデジタル化から着手しました。次のステップとして、足元では貿易データの活用を推進しています。
こうしてデジタル化を順番に推進してきて、Excelや電話、メール、手書きといったアナログなツールから脱却するモデルケースとなる企業が徐々に増えてきています。
業界全体に貿易DXを啓蒙する目的で今年から当社が始めた「Shippio Advanced Award」では、貿易DXのモデルケースとなる企業6社を表彰しました。

将来的には、物流・商流・金流そして情報の流れを「Shippio Platform」に集約し、貿易に関わるあらゆる業界の人々が参画することで、その利便性を享受できる状態を目指します。その先に、アドバンストされた貿易を起点に「産業の転換点をつくる」という私たちのミッション実現を見据えています。
(構成=UNICORN JOURNAL編集部)











































