事業活動においては、商品を仕入れて販売するにしろ、原材料を加工して商品を製造し、それを販売するにしろ、必ず資金の支出が先行し、それが回収されるまでの期間、資金は外部に流出している。金融の第一の機能は、この流出している資金、即ち、運転資金を事業者に供給することにあるわけである。また、事業活動には、店舗、物流施設、製造装置等が必要になるから、金融の第二の機能は、その購入資金、即ち、設備投資資金の供給になるのである。
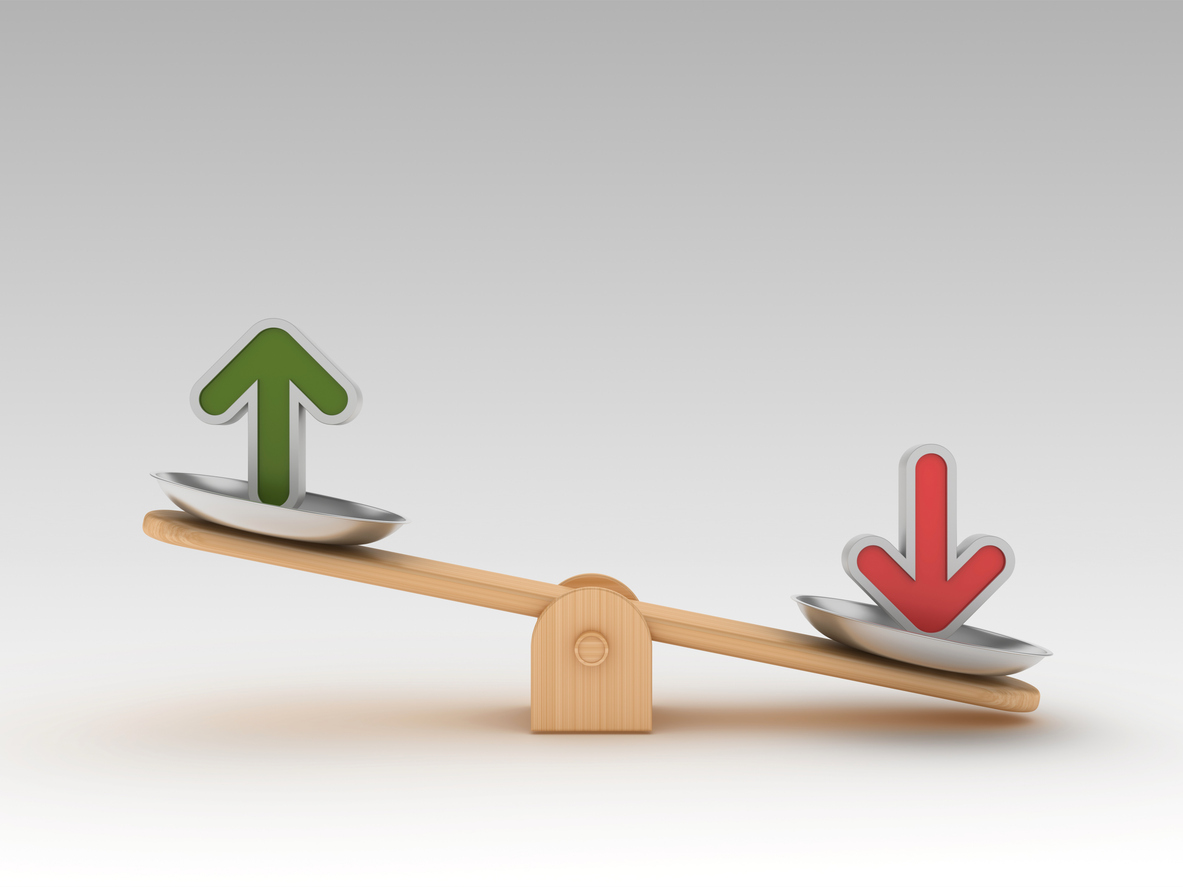
porcorex/iStock
金融の立場からは、資金供給の方法として、弁済条件を一切付さない資本の供給によるものと、逆に、弁済期日と金利とを厳格に約定する融資、もしくは社債の引受によるものがあり、事業者の立場からは、調達資金の計上区分として、それぞれ資本と負債になる。
資本は、金利がなく、弁済期日もないので、事業者に極めて有利のようにみえるが、金融の本質は、ただほど高いものはないという俗言につきているわけである。つまり、出資、即ち、資本の供給には、事業経営に介入できる権利が付されているので、事業者としては、資本に対する利益還元を負債の金利費用よりも高くすることで、出資者を満足させて、経営介入を阻止する必要に迫られるのである。
事業活動は不確実性に満ちていて、計画は常に狂い続けて、出金の必要あるときに、手元資金の枯渇する事態は生じ得るから、一定の資金の余裕は不可欠で、その際、弁済や利払いの必要のない資本は非常に重要な役割を演じている。そして、事業の異なるのに応じて、事業に内包する不確実性の程度も異なるから、必要な余裕資金額や資本額も異なってくる。いうまでもなく、事業に伴う不確実性が大きいほど、より大きな余裕資金や資本が必要になるわけである。
資本構成とは、必要資金の総額における資本と負債の構成比のことであり、最適資本構成とは、事業の不確実性に対して最適となる資本構成のことである。最適とは、資本が過大であれば、資本利潤率の低下を招き、資本が過少であれば、破綻確率を高めてしまうので、過大でも過小でもなく、不確実性を吸収するのに過不足のないことを意味している。そして、この最適資本構成を決めることこそ、金融理論の中核的課題なのである。






































