『日本の名門高校 – あの伝統校から注目の新勢力まで –』(ワニブックス)の発刊を記念しての連続記事の2回目。
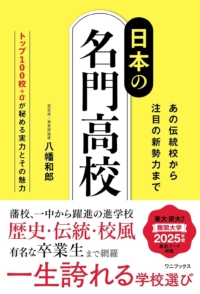
旧制一中とは何であるかは、明治19年に各県で乱立していた中学を一つの尋常中学に統合して、内容も統一した。そのときの尋常中学の系譜をひくものがいわゆる旧制一中だ。
そこで、47府県ごとにどこが一中で現在もトップ進学高かを解説する。今回は東日本編である。文中で最初に校名が書いているのが、いわゆる旧制一中とされる学校である。

2025年度「旧制一中」の都道府県内 東大・京大 合格者『日本の名門高校 – あの伝統校から注目の新勢力まで -』より
北海道・東北
北海道では、札幌南があいかわらず東大進学数トップだが、北海道大学については、キャンパスが地理的にも近い札幌北が優勢だ。
青森県では城下町である弘前に国立大学も一中もあったのだが、人口が少なく、現在は八戸(二中)や青森(三中)と拮抗。
岩手県では、宮沢賢治や石川啄木の母校である盛岡第一が県内でひとりがち。
宮城県では仙台第一は、通学区域が下町であり、インテリ層が多い仙台第二が優位。
秋田県は秋田がトップ。
山形県では、県が山形東にてこ入れをしていて、一定の成果を上げている。
福島では、郡山市にある安積が一中で、磐城が二中、福島が三中(安積は郡名)。安積と福島が競う。
関東
茨城県では水戸城三の丸跡にある水戸第一。筑波研究学園都市などで成長した土浦第一が優位。
栃木県では宇都宮。栃木県第一中学校が1881年に東京・上野で行われた第2回勧業博覧会を見学に行ったのが、修学旅行のルーツ。
群馬県では前橋と高崎がライバルで、前高(まえたか)・高高(たかたか)の定期戦が各種競技で開かれる。
埼玉県の浦和は全国の公立の雄。ノーベル物理学賞受賞の梶田隆章が出た川越は三中。
千葉県の千葉も公立の雄で中高一貫も。トップは私立の渋谷幕張












































