『日本の名門高校 – あの伝統校から注目の新勢力まで -』(ワニブックス)という新刊を出した。よく似たテーマの本は3冊目で、これまでも多くの方に読んでいただいている。この本で項目として取り上げているのは、100名門高校だが、日本のさまざまな高校を体系的に取り上げている。
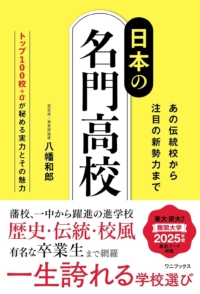
もちろん、自分の高校の自慢話をしたいとか、受験の参考にもなるが、それと同時に、ビジネスやお付き合いのときの話のタネにも役立つ。また、戦前から最近までの変化を説明しているので、たとえば、家族の中でのコミュニケーションをよくするのにも役立つと思う。内容豊富でコスパもいい本ということでおすすめする。
ここで挙げている表は、東大・京大の合格者の1950年代からの推移である。戦後の教育史がここに集約されている。

『日本の名門高校 – あの伝統校から注目の新勢力まで -』より
とくに目立つのは、1950年代には、東大トップは旧東京一中の日比谷高校、京大トップは旧京都一中の洛北高校で、それに東京、京都の公立高校が続いていたことだ。
ここでは、洛北高校を題材に歴史を振り返ってみよう。ちなみに、洛北高校は池田信夫先生の母校である。

京都府立洛北高等学校・附属中学校 Wikipediaより
湯川秀樹博士らノーベル賞受賞、第一号・第二号の母校
京都では、明治2年(1869)、64の小学校が市民主導で開校した。いわゆる「番組小学校」である。「民間に学校を設けて人民を教育せんとするは余輩昔年の宿志なりしに、いま京都にいたりてはじめて其実際をみるを得たるは、其悦あたかも故郷に帰りて知己、朋友に逢ふがごとし」と福沢諭吉を感激させた。
京都御苑内の学習院を淵源とし、明治3年(1870)に開校して京都府中学校となり、のちに洛北高校となった。京都府中学校は、明治9年(1876)に仮中学と改称、明治12年(1879)に京都府中学となった。そして、明治19年(1886)の「一県一尋常中学校令」(第一次中学校令。一府県一校設置の原則)を受けて、同20年には京都府尋常中学校となった。









































