日本は街中に必要がないのに、機械化したものや、毎回使用料を払うような「非合理的かつ無駄」なシステムが数多く存在しています。
例えば、交通公共機関はその典型です。

winhorse/iStock
バスや地下鉄電車などは区間ごとにいちいち料金を払う仕組みが主流ですが、他の国だと様々な乗り放題チケットがあったり、一定金額を超えると、プリペイドカードで自動的に料金が計算されて乗り放題になると言う仕組みが一般的です。
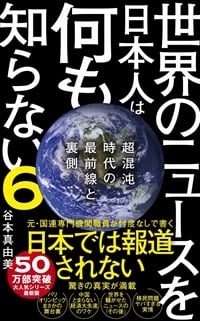
乗り放題のチケットも1日券や1週間だけ、2週間だけ1ヵ月だけといったものがあって、非常に柔軟性があります。
例えば、ロンドンの交通局ではそのような仕組みになっています。バスや鉄道地下鉄の料金もゾーン制になっていて、区間を超えると料金が変わり、自動的に計算されます。
地方に行けばもっと細かくなっていることもありますが、しかし、その仕組みは日本に比べると極めてシンプルです。
仕組みや機械はシンプルであればあるほど、設計も設置も修理も簡単で、メンテナンスが楽であり、使う人の訓練も簡素です。故障箇所がどこかも特定しやすい。
さらに特に現在ではあえて電子化する部分を最小限にすることでリスクを回避することが可能です。
例えば私のかつての職場の一つは、ドアには一切電子ロックがありませんでした。これは職場の技術者がIT業界の大ベテランで、元軍人もいたので電子制御を一切信用していなかったのが原因です。
何らかの形でハッキングされたり停電した場合、部屋に閉じ込められたり、機密を盗まれてしまいます。下手したらテロリストや強盗に閉じ込められたり命を奪われるのです。
これは職場が危険地帯や途上国で仕事をしてきたために、最悪の状況を想定していたからです。
電話は昔ながらの黒電話です。これもあえて高度なものを入れないことで、メンテナンスや故障を防ぎ、ハッキングされないことを想定したものです。
ビジネスや社会の仕組みに関しても全く同じです。極めてシンプルにしておけば、誰でも理解がしやすいですし、運用も制度の変更も極めて手間がかからず、作業工数は最小となり、リスクを回避できます。



































