
Business/iStock
経営者をサポートする士業と呼ばれる専門家がいます。難関資格を保有する専門家として尊敬を集める一方、同じ資格保有者でも仕事内容や方針、そして能力も当然異なります。
「あなたの期待に応えるプロ士業を選ぶためには、それぞれの士業にどんなことを頼めるのか、知る必要があります。税理士と公認会計士の違いについて、一般的に言われていること以外のポイントをお伝えしますので、参考にしてください。」
そう語るのは士業向けの経営コンサルタントで自身も士業(特定行政書士)である横須賀輝尚氏。同氏の著書「プロが教える潰れる会社のシグナル」から、プロ士業の見抜き方を再構成してお届けします。
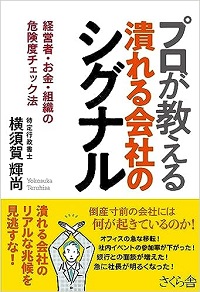
個人事業主の確定申告は、もはや自分で、しかもオンラインで済ませられる時代です。国税庁のウェブサイトも昔に比べてだいぶ使い勝手がよくなりました。ですから、基本的に税理士については「法人の経営者がどのように活用するか」という視点で解説をしていきます。
ちなみに、個人の確定申告を税理士に依頼する場合は、コストとして考えれば数万円から10万円前後が現在の相場です。
さて、税理士と公認会計士。税理士でも「会計士の先生」等と呼ばれることもあり、同一に考えている人もいますが、資格としては異なります。細かい成り立ちや法律の解説をしても面白くないでしょうから、実態を中心に解説していくことにします。
まず、税理士は税理士法に基づいた「税務、税金のプロ」です。これに対して、公認会計士は、同じく公認会計士法に基づいた「監査のプロ」です。
税理士は、会社の中から税務書類をつくる。公認会計士は、外から財務の監査をする。このように「中から」が税理士、「外から」が公認会計士と考えると、わかりやすいでしょう。
ちなみに、税理士の数は78714人(令和2年)。公認会計士は37343名(令和元年)。士業の中でも、税理士は突出して人数が多いのも特徴です。
さて、ではなぜ税理士と公認会計士が混同されてしまうかといえば、それは独立した公認会計士は、「税理士登録をして税理士として開業することがほとんど」だからです。
これも案外知られていないことなのですが、公認会計士は試験を受けずとも税理士になることができます。細かいことを説明しだすとキリがないので簡潔にしますが、資格制度というのは、資格を保有することと、その資格を持って活動を行うというのは、また別のことなのです。
資格を持っているだけの人を「有資格者」と呼びます。この有資格者が、税理士なら税理士会に登録することによって、晴れて税理士になれる。そういう仕組みなのです。
ちなみに、試験に通らずとも、弁護士も税理士登録が可能です。ですから、弁護士と税理士両方の資格を持ってダブルライセンスで仕事をしている士業は、弁護士の資格をつかって、税理士登録をしている場合がほとんど。ですから、その場合は税務の知識があるかどうかというと謎です。
話をもとに戻しましょう。公認会計士は独立開業する場合、税理士登録をして税理士としても開業するとお伝えしました。なぜ、公認会計士として独立せず、税理士・公認会計士として独立することが多いのか。それにはこんな背景があります。
まず、公認会計士を目指す人の多くは、監査法人に就職します。監査法人とは、監査を業務とする法人。国内では、BIG4と呼ばれる「有限責任あずさ監査法人」、「新日本有限責任監査法人」、「有限責任監査法人トーマツ」、「PwCあらた有限責任監査法人」が有名です。このような監査法人に就職し、資格取得を目指します。
合格後、勤務のまま監査法人を勤め上げる人もいれば、独立する人もいる。そういう流れなのですが、監査法人の仕事って、ほとんど上場企業とその準備企業に対しての仕事なのです。つまり、大企業相手にしかできない仕事が監査、つまり公認会計士の仕事なんですね。
税理士であれ公認会計士であれ、独立開業することになれば、クライアントのほとんどが中小企業です。大企業を相手にすることってなかなかありません。そうすると、個人で監査の仕事を受けるということが、世の中的にほとんどなく、登録できる税理士の資格を併せて独立せざるを得ない。そういう状況なのです。
ですから、税理士も公認会計士も、結構混同されて考えられてしまうわけです。














































