一方で「仲裁」も伝統的な紛争解決方法である。日本での相続問題や土地紛争それに離婚や親権問題など民事関連では、旦那さんなど地元有力者が「まあまあ」という姿勢で双方の当事者の間に入り、一定の調停を果たす歴史があったから、「仲裁」は馴染みの方法ではある。
しかしその場合には、紛争当事者双方による仲介者への認知と尊敬が前提となっていた。「あの方が言われるのだから、この辺りで手を打とう」という気持ちにさせる威厳や声望を当事者双方が持たなければ、この方法は成功しない。
ロシアによるウクライナ侵略戦争でもイスラエルのガザ地区への猛爆にしても、世界的な「仲介者」が不在なのだから、廣田がいうように「現実性に乏しく、夢のような話」(170頁)なのだが、「国際世論」がもつ「仲介」機能に私は期待したい。
実体的な和平法則のうち「過酷条件回避の法則」は一般論としては納得できる。本文でも第1次世界大戦後のドイツへの過酷な賠償を事例とし、「和平の内容に過酷な条件は避けたい」(176頁)とされた。なぜなら、「和平は、将来指向」(177頁)だからである。
そうはいっても、病院、学校、発電所、水道施設、マンション、アパートなど市民生活の根幹をなす都市装置が一方的に破壊され、破片が散乱して、がれきの山と化した映像を毎日テレビニュースで見ている世界各国の国民感情からすると、その片付けと再建の責任はどこが受け持つのかという難問に悩んでしまう。
ウクライナ全土でもイスラエルのガザ地区でも「将来指向」だからこそ、破壊した当事者の責任が一番先に問われるという意見も強まるのではないか。「ひたすら前を向いて知恵を絞るべき」(178頁)ことは分かるが、誰が、どこが、真っ先に「前を向くのか」もまた重要である。かえすがえすも、組織が硬直化した国連の機能不全が悩ましい。
「第4章 パラダイムシフト」については、「資本主義というパラダイムを転換すれば、そのあらかたの難問を解決することができる」(187頁)という指摘も含めて、拙著『社会資本主義』でも論じた部分があるので、ここでは割愛することにしたい。
「異次元」論争で始まった今年の年末は、本書の「和平法則」に学び、身近な争いから人類の危機を招く戦争にまで目配りして、来年の「平和」に向けての思索と議論を深めよう。
■
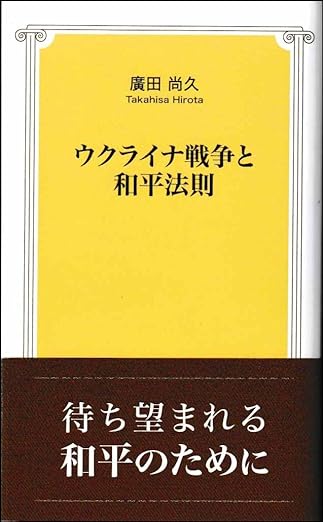
『ウクライナ戦争と和平法則』
提供元・アゴラ 言論プラットフォーム
【関連記事】
・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」
・大人の発達障害検査をしに行った時の話
・反原発国はオーストリアに続け?
・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』
・強迫的に縁起をかついではいませんか?










































