「催促相場」という言葉があります。市場の期待値が上昇し、決定者の判断を促すことを言います。主に民間企業の株価の反応の際に使いますが、政府の判断にじれている場合でも使います。
日銀が現在行っている大規模金融緩和について一体いつ、金融正常化になるのだろうというのがほぼ全ての市場関係者の関心の的であります。不思議と「大規模緩和をずっと続けてほしい」という声はあまり聞かない気がします。住宅ローンを抱える方や借り入れがある企業の声は「金利を上げないでほしい」が本音ですが、それは利害関係のある当事者の声であってそれをあまり重視していると正しい判断が出来なくなるものです。

日本銀行の植田総裁 日本銀行HPより
ブルームバーグに興味深い記事が掲載されています。10月16日の夕方の会見で財務省の神田財務官が「為替の激しい下落時、国は『利上げか為替介入で対抗』」と述べたとあります。その記事には触れていないのですが、私は奇妙な気がしたのです。財務官が為替防衛について「利上げ」ということを言うのだろうか、と。
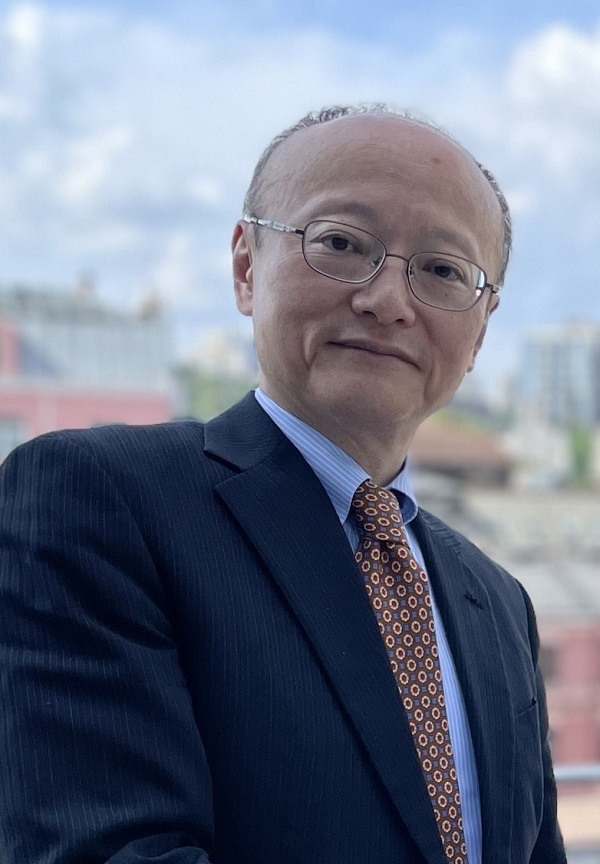
神田真人財務官 財務省HPより
日銀は財務省と深い関係があるし、各種国際会議でも財務大臣と日銀総裁が一緒に参加するケースはしばしばあり、情報や問題の共有はかなり深く行っています。但し、日銀の目的はインフレ率と失業率の調整機能であり、為替管理は日銀の機能にはないのです。これは昔から財務省の管轄であり、為替介入を主導するのは財務省であります。
それを考えると神田財務官がなぜ、「利上げ」対抗を述べたのか、氏の深謀なのかしっくりこないのです。
時を同じくして日経が日経マネーの記事の転載として「マイナス金利撤廃をためらうな 緩和は弱者を救わない エミン・ユルマズの未来観測」という記事を電子版に掲載しています。ユルマズ氏はトルコ人で東大卒業後、野村證券を経て金融に関する民間塾、「複眼経済塾」の主要メンバーなど国際エコノミストとして活躍されています。この記事は丁寧で読みやすいものです。現在の金利水準が多少上がっても「高が知れている」と断じ、それよりも不動産などの資産インフレを抑え、将来の経済激変時の金利のバッファーを確保することと述べています。これは私がずっと述べてきたことと全く同じです。










































