忘れるのも脳にとっては「一苦労」なようです。
私たちはこれまで忘却は脳の怠惰によって起こる劣化現象だと考えていました。
しかしアイルランドのダブリン大学トリニティ・カレッジ(TCD)で行われたマウス研究により、忘れるためには記憶を保持している脳細胞たちがわざわざ活性化する必要があることが示されました。
言い換えれば、脳は汗水たらして苦労の末、やっと忘れることができるのです。
この結果は、忘却は脳の怠惰によって神経接続が崩壊していく受動的なものではなく、脳の積極的な働きかけが必要な、能動的なプロセスであることを示します。
しかし知識は力という言葉があるのに、なぜ脳はわざわざ労力をかけて記憶を忘れようとするのでしょうか?
研究内容の詳細は2023年8月16日に『Cell Reports』にて公開されました。
記憶の本質はエングラム細胞にある
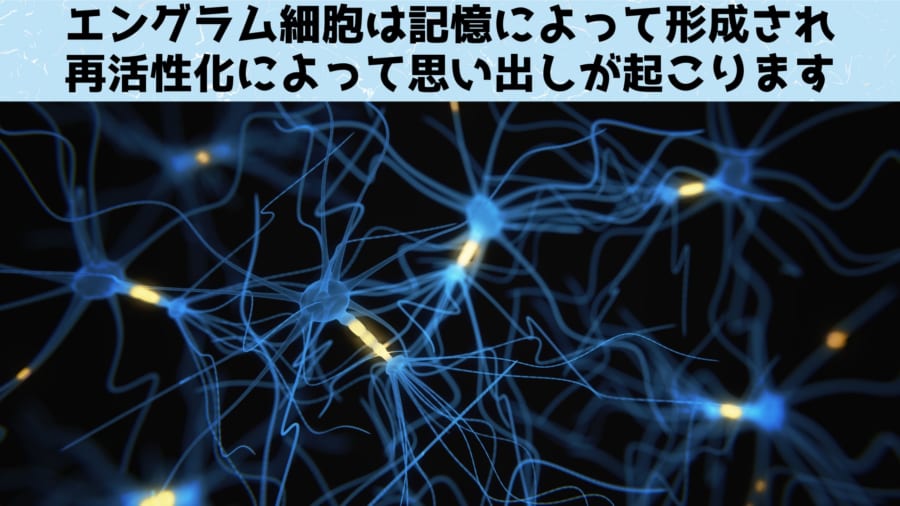
人生は無限の織りなす瞬間の連続、一つ一つの体験が私たちを彩ります。
しかし残念なことに、その多くのが、時の流れとともに闇の中に消えてゆきます。
これまでの常識では、記憶の喪失は神経回路の劣化によって発生すると思われていました。
まるで古い電子部品が徐々に錆びて劣化するように、使われない知識や思い出は消え去っていくと考えていたのです。
しかし近年の研究により、私たちの記憶が「エングラム細胞」と呼ばれるニューロン集団に保存されていることがわかってきました。
私たちが何らかの学習を行うと、脳細胞の接続に物理的変化が発生し、記憶の物理的な痕跡(エングラム)を構成します。
エングラム細胞はそのような記憶にともなう物理的変化を発生させた細胞集団であり、個々の記憶の保存を担当しています。
たとえば今ここで「ニホニウムは日本人が発見した元素」という情報に触れると、脳内ではその情報に対応したエングラム細胞たちが出現するのです。
そして記憶を呼び出すときには、記憶に対応するエングラム細胞たちの再活性化が起こることが明らかになってきました。
また「ニホニウムの原子番号は113」という追加の情報を覚えると、さきほどのニホニウムの記憶に対応するエングラム細胞が再活性化されるとともに、追加の原子番号にかんする情報を取り入れた新バージョンにエングラム細胞が生まれ変わります。
このようにエングラム細胞が出現や更新を繰り返すことで私たちの記憶が作られ更新されているのです。
私たちの記憶とは、エングラム細胞の生成によって作られ、活性化によって思い出され、再編成によってバージョンアップを繰り返していくのです。
しかしこれまでの研究ではエングラム細胞の生成や再活性化に主眼が置かれており、忘却が起きた時のエングラム細胞にどんな変化が起こるかは詳しく解っていませんでした。
単にエングラム細胞が解散されてしまうのか、エングラム細胞が別のエングラム細胞に取り込まれるのか、再活性化ができなくなっているだけか、わからなかったのです。
そこで今回ダブリン大学の研究者たちは、マウスが記憶を失うときに、エングラム細胞に何が起こるかを可視化してみることにしました。
といっても、人間と同じようにマウスたちも記憶を簡単には失ってはくれません。
意識して覚えることはできても、意識して忘れることはできないからです。









































