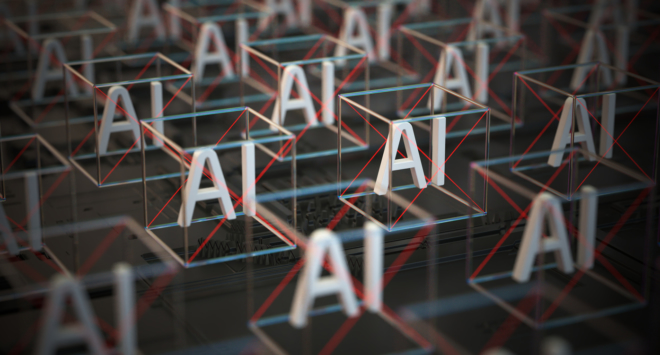
Just_Super/iStock
人間が作ったような文章、画像を作成する生成AI(人工知能)フィーバーが起きています。AIは人々の暮らしに浸透し、技術、社会、経済、政治を含め、時代を変える「100年に一度の衝撃」になるかもしれないそうです。
雑誌「プレジデント」や「ダイヤモンド」が「ChatGPT仕事術大全」「ChatGPT完全攻略」という大特集を組んでいます。ざっと目を通していましたら、10日午後8時の「池上彰のニュースワイド」(テレビ朝日)で「話題の生成AIの仕組み」という番組をテレビで放映していました。
池上彰氏はどんな問題でも消化し、分かりやすく解説するのが特技です。テレビ、新聞、出版、教育など多くの分野にでて、なんでもこなす。この番組を見ながら感じたのは、「著作権侵害に鈍感な点では、池上氏もChatGPTも変わらない」ということでした。
池上氏は番組制作チームを使って、幅広く情報源、文献にから材料、データを集め、ストーリーを作り、上手に話す。池上氏はどこから情報やデータを集めたかいちいち言わない。厳密にいうと、フェアではない。
著書でも参考文献の掲載はしないか、あっさりとしており、いつも池上氏は著作権侵害をどう考えているのだろうと、感じていました。この番組でもそうでした。放送番組には著作権があり、第三者は勝手に流せない。それなのに番組の制作・出演者である池上氏は恐らく他人の著作権を尊重していない。不思議な二重構造です。
ChatGPTは巨大な規模のコンピューター、半導体を使って、膨大なデータベースで学習し、成果を瞬時に示す。池上氏に比べ、ChatGPTは企業戦略、商品開発、生産性の向上、採用試験、会議資料、企画書の立案など、使途は無尽蔵ですから両者は比較の対象にはならない。比較できるのは、著作権侵害に対する感度が似ているという点です。







































