目次
毎年払う自動車税にはどんな意味があるの?
本当に道路に関係する場所へ使われているのか
毎年払う自動車税にはどんな意味があるの?
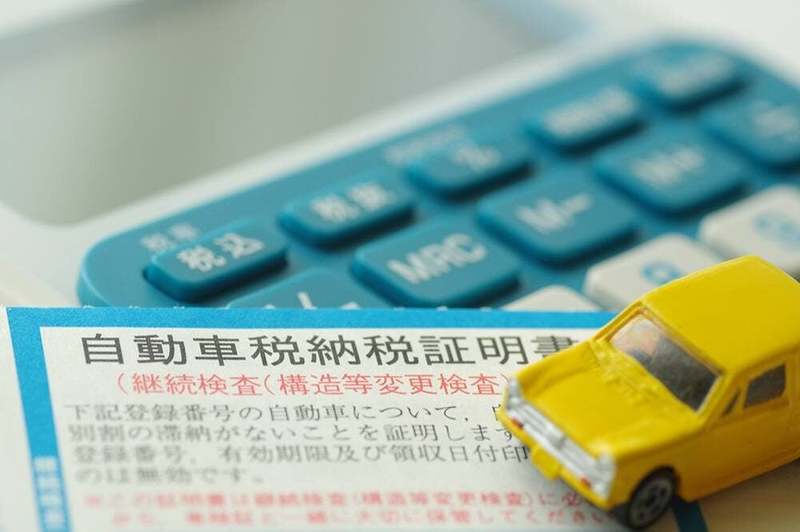
例年、4月下旬から5月上旬にかけて届く自動車税の納税通知書。自動車ユーザーは年間に3万円~6万円程度を支払っているわけですが、この税金は一体何に使われているのでしょうか。
自動車税は、昭和25年7月31日に施行された地方税法に基づいて徴収される税金です。道路運送車両法第4条の規定により、自動車の所在する都道府県において、所有者に対し徴収が行われます。
現在では「自動車税種別割」と名前が変わりましたが、税の内容は従前の自動車税とほぼ変わりがありません。
総務省のホームページには、自動車税・軽自動車税種別割について、「自動車・軽自動車に対し、その所有の事実に担税力(税金を負担する能力)を見出し、その所有者に課する普通税(中略)。道路等との間に極めて直接的な受益関係を持つ特殊な財産税としての性格を持つほか、道路損傷負担金的な性格を持ちます。」と記載されています。
本当に道路に関係する場所へ使われているのか

記載事項を見ると、道路損傷負担金、つまり道路に関係する使用目的で徴収されているように思えます。
実際に、税金の中には「目的税」と言われる、使い道が決められている税金があります。しかし、自動車税種別割(以下自動車税)は目的税には当たりません。
自動車税の課税団体は都道府県、軽自動車種別割(以下軽自動車税)の課税団体は市区町村となっています。前述したとおり、この2つは地方税です。また、つまり、自動車税として納付された税金は、各地方公共団体が管理し、一部は県道や市道などの保全改修などに充てられることもありますが、福祉や教育、公共物の整備、警察・消防・救急といった行政機関の維持管理などにも利用され、必ずしも車に関係することに使用されているとは言えないのです。









































