財源が不足なのに手を広げすぎ
そんなに何から何まで、国ができるのだろうか。そんなにたくさんの政策を背負いこむ財源はあるのだろうか。国でできないことも多いのに、できると錯覚する。国でできることがあっても、財源が足りない。岸田首相の施政方針演説を読んで、多くの人がそう感じたのではないでしょうか。
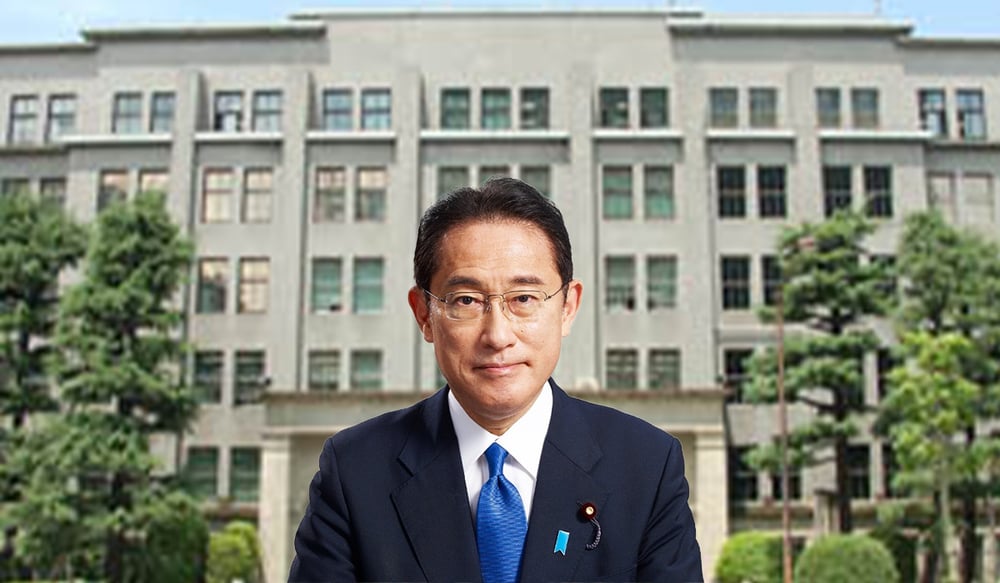
岸田首相 財務省HPより
岸田氏に限らず、歴代首相の多くに感じてきたことです。「金融の大規模緩和で物価を2%引き上げられる」と信じた黒田日銀総裁の異次元緩和も、できないことをできると錯覚した典型的な実例でしょう。
首相は「われわれは再び歴史の分岐点に立っている」として、明治維新、アジア太平洋戦争の終戦(敗戦のこと)に続き、現在が大きな転換点だ」と、姿勢方針演説で強調しました。確かに何から何までが音をたてて、変わり始めています。
ロシアによるウクライナ戦争、気候変動(温暖化)、感染症対策、地球規模の問題、格差問題などをあげました。さらに脆弱な世界の供給網、エネルギー・食料危機、人への投資不足、グローバリゼーションの変質に言及しました。「こうした現実を前に新たな方向に足を踏み出す」と。
政府がやるべき仕事がどんどん増えています。政府に期待されることが今や森羅万象に及びます。財源が不足し、巨大な財政赤字に陥っているのですから、「政府がやるべきこと」と「政府にはできないこと」を原点に戻って、線引きし直す局面です。首相が好むスローガン「新しい資本主義」の本質的な問題はそこにある。
「財源が足りないから国債(国の借金)でやらざるを得ない」ではなく、「効果があるかないか分からないことまで政府が手をだすから、財源が不足し、国債に頼る」のだと思います。原因と結果の順序が逆です。
財源は税収、借金(国債発行)、社会保険料(社会保障負担)などです。このうち、「政府の子会社」(安倍・元首相)に位置付けられた日銀が財政ファイナンス(実質的な国債の買い上げ)を続けていますから、借金に歯止めがかからなくなっている。
増税は国民の抵抗が強いため、借金(国債)に走る。「子会社だぞ」と言われている日銀は抵抗せず、際限なく残高が膨らんでしまった。
社会保険料(年金、医療、介護など)は実質的な税金です。その負担増は勤労者と企業に対する「見えざる増税」で、「見えにくい」から抵抗が少ない。22年度の保険料収入は74兆円に増え、税収の68兆円を上回る。













































