「食オク」が予約困難が助長するかもしれない理由とは
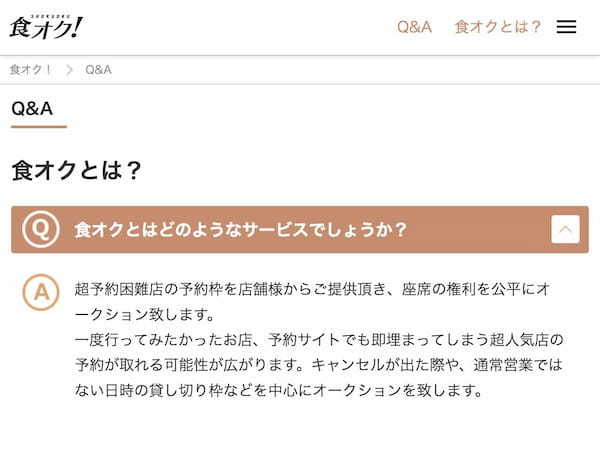
参画した飲食店の考えとしては、「常連客以外で予約したい人がいてもこれまで予約を受けられなかった。この要望に応えられることや食文化を守ることに貢献できることが魅力だ」と話す。
また利用者は、どうしても利用したい際に店の選択肢の間口が広がるという声も挙がった。とはいえ、従来は1円も支払う必要がなかった「予約権」に莫大なお金がかかることからも、「富裕層向けのサービス」ということは瞭然だ。
初めてのサービスだけに物議を醸すことは当然として、課題は依然と多い。
例えば転売を懸念して作った公正なサービスだと主張するが、オークションシステムである以上、需要が上回った場合は価格がつり上がることは必至だ。また食オクで落札した予約の権利は転売厳禁としているが、何かしらの転売対策システムを取り入れることも必要だろう。
また、「食オク」を通じて、常連が増え、さらに予約困難が助長されるという懸念もぬぐえない。食オク側は、「食オクで落札して高級店へ足を運んだ際、次回の予約は取れない」としているものの、あるお客が立て続けに落札して何度か店へ足を運んだ場合、事実上“常連”として認められることが考えられるからだ。
結局はモラルの問題ばかりが目につき、参画する飲食店への印象も深刻化することも懸念材料だ。
一方で、コロナに罹患したお客によるキャンセルやダブルブッキングしてしまったお客によるキャンセルなど、飲食業界にとって近年特に深刻な直前キャンセルによる食材ロスや不利益への対策としては極めて有効だ。
今後、食オクは運営しながら徐々に対策を講じると話している。そしてやがてはパリやニューヨークといった海外の予約困難店でも展開することを示唆している。物議を醸しているからか、秋以降、オークションがオープンになることは無く、動きは鈍いものの、今後も注視したい新サービスだ。
文・佐藤 良子/提供元・DCSオンライン
【関連記事】
・「デジタル化と小売業の未来」#17 小売とメーカーの境目がなくなる?10年後の小売業界未来予測
・ユニクロがデジタル人材に最大年収10億円を払う理由と時代遅れのKPIが余剰在庫を量産する事実
・1000店、2000億円達成!空白の都心マーケットでまいばすけっとが成功した理由とは
・全85アカウントでスタッフが顧客と「1対1」でつながる 三越伊勢丹のSNS活用戦略とは
・キーワードは“背徳感” ベーカリー部門でもヒットの予感「ルーサーバーガー」と「マヌルパン」









































