ある種の大腸がんは手術しなくても免疫療法で治癒できる!?
2週間前のNew England Journal of Medicine誌に「PD-1 Blockade in Mismatch Repair– Deficient, Locally Advanced Rectal Cancer」というタイトルの論文が報告された。特別な条件の直腸がんに対しては、手術しなくてもがんを治癒できる可能性を示した画期的な論文である。
この臨床試験では、DNAミスマッチ修復酵素が欠損しているステージII・IIIの局所直腸癌患者に対して術前に抗PD-1モノクローナル抗体(dostarlimab)を3週間ごとに6か月間投与する予定で始められました。治療後には、標準的な化学放射線療法や手術が行われる予定でしたが、12例では完全に腫瘍が消失し(あと4例は6か月の投与を終えていない。
そのうち2例は、まだ、臨床的効果を調べられていない)、その後、最低6ヶ月の経過観察中に画像診断による再発・転移は認められていないとのことだ。
一般の大腸がんでは、免疫チェックポイント抗体の効果は5%程度だが、DNA修復遺伝子(あるいは、ある種のDNA合成酵素遺伝子)異常のある大腸がんでは有効率が60-70%という報告があった。
これらの試験では、標準療法終了後に免疫チェックポイントが投与されていたので、今回わずか12例であるが、患者さんの免疫力が傷ついていない条件では、さらに有効率が高く、しかも、完全にがんが消えているという結果は驚きだ。
1990年前後に大腸がんの多段階発がんモデルがジョンス・ホプキンス大学のボーゲルシュタイン教授とユタ大学のホワイト教授の共同研究で報告された。誰も触れてくれないので、ここで述べておくが、ホワイトーナカムラ多型マーカーが利用できたことがこの先駆的な研究につながっている。
多くの年配のアメリカ研究者はこれを知っているが、ほとんどの日本人は知っていても、これに言及しない。とはいえ、こんなことを自分自身で言及しないといけないのは個人的には悲しい限りだし、残念ながら、日本の科学研究の評価が公平・公正でない証でもある。
話を戻すと、多段階発がん説では、遺伝子異常が蓄積されるほど、より悪性度の高いがんができるはずだったが、遺伝子異常の多い(ミスマッチ異常陽性)の遺伝性大腸がんの予後が比較的いいのが謎だった。
2000年以降、がん免疫に関心を持って研究しているが、この謎は遺伝子異常の極端に多い大腸がんでは、それによって生み出されるネオアンチゲン(がん特異的な抗原)が多いため、ネオアンチゲンを標的とするTリンパ球が腫瘍組織内に多くなっていることで説明が可能だ。
がんが大きくなる条件では、腫瘍細胞を介して、がん細胞を攻撃する免疫が抑えられている。抗PD-1抗体や抗PD-L1抗体などの免疫チェックポイント抗体は、このがんに対する免疫を抑えている分子や細胞を抑制する働きがある。簡単に言うと、がんを守っている守備要員を抑え込むのだ。
しかし、がんに対する攻撃側が弱いと臨床的な効果は期待できない。ネオアンチゲンが多いと、一般的には攻撃側のリンパ球が多いため、攻守の形勢が一気に逆転し、そうなると、がんを攻撃するリンパ球がさらに元気になって増えてくるのだ。この論文では一部のミスマッチ修復遺伝子や酵素しか調べられていないが、ゲノム解析による遺伝子異常数を基準にするともっと多くの患者に適応可能だ。
この論文から学ぶ最も重要な点は、標準療法が終わってからしか、新しい治療法が検証できないという国内の硬直した思考力だ。抗がん剤で免疫力を低下させてから、免疫療法を試みることが正しいと信ずる非科学力思考力は、日本の喜劇であり、がん患者さんにとっては笑えない悲劇である。
コロナウイルス感染症対策で、日本は科学力の無さを世界に知らしめた。政治家や官僚の科学リテラシーの欠如がこの国を危機的状況に追い込んでいる。
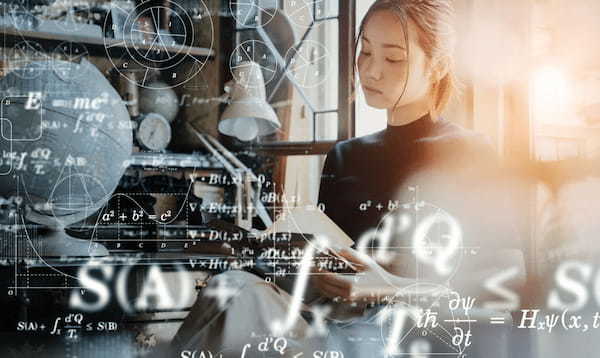
編集部より:この記事は、医学者、中村祐輔氏のブログ「中村祐輔のこれでいいのか日本の医療」2022年6月18日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。
文・中村 祐輔/提供元・アゴラ 言論プラットフォーム
【関連記事】
・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」
・大人の発達障害検査をしに行った時の話
・反原発国はオーストリアに続け?
・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』
・強迫的に縁起をかついではいませんか?









































