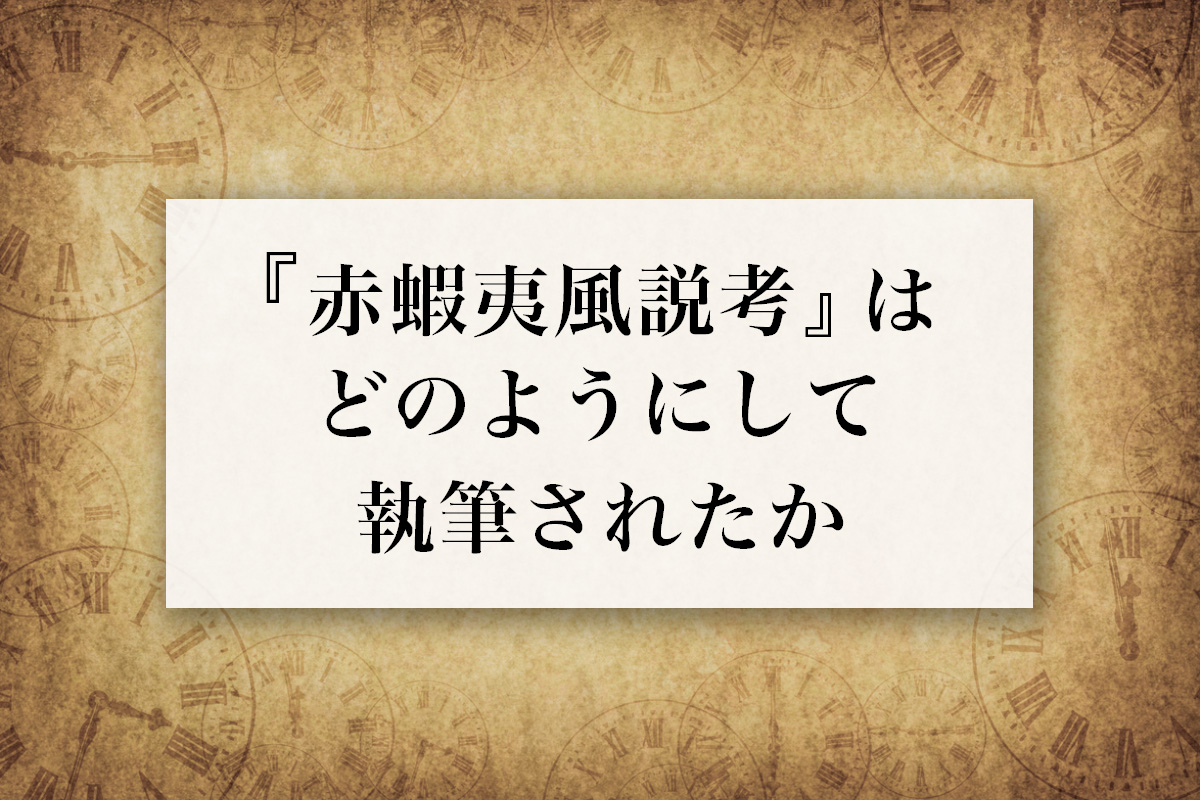
(前回:『赤蝦夷風説考』の著者、工藤平助とは何者か?)
田沼意次(1719~88年)の蝦夷地(現在の北海道)開発計画の発端となった工藤平助(1734~1801年)の著作『赤蝦夷風説考』は、天明3年(1783)に完成した。同書は、ロシアの東方進出の歴史や北海道・千島列島・カムチャツカ半島・ロシアの地理的位置について正確に記述した初めての日本語文献として評価されている。
では、工藤平助は『赤蝦夷風説考』を執筆するにあたって、ロシア情報や蝦夷地情報をどのようにして入手したのだろうか。
平助はオランダ語ができなかったが、広範な人脈と情報収集能力を駆使して同書を執筆した。平助は仙台藩の医師として活躍しながら、長崎のオランダ通詞(通訳)、蘭学者、松前藩関係者など、多様な人物との交流を通じて、海外情勢や北方地域の情報を収集した。本稿では、平助がこれらの情報をどのようにして入手し、『赤蝦夷風説考』を完成させたのかを紹介したい。
1. 平助の広範な知的ネットワーク
工藤平助は、仙台藩の医師でありながら、その活動範囲は医学に留まらず、蘭学、地理学、海外情勢への関心にまで及んだ。
彼の長女である只野真葛の随筆『むかしばなし』によれば、平助は20代半ばからその名声が広まり、30歳前後には長崎や松前といった遠方からも弟子入りを希望する者が訪れるほどの評判を得ていた。この名声は、平助の社交的性格と、多様な分野の知識人との交流に基づくものであった。
平助の交友関係は、蘭学者(前野良沢、大槻玄沢、桂川甫周)、長崎の通詞(吉雄耕牛)、さらには松前藩関係者(湊源左衛門)など、幅広い層に及んだ。これらの人物との交流を通じて、平助は長崎や蝦夷地を訪れることなく、江戸にいながらにしてロシアや蝦夷地の詳細な情報を入手することができた。
蘭学者のネットワークと松前藩関係者からの情報が、『赤蝦夷風説考』の執筆に決定的な役割を果たしたのである。











































